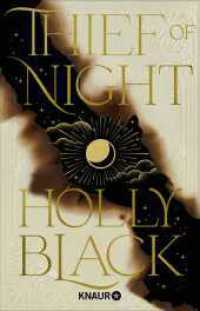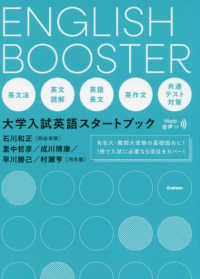内容説明
夕闇のなかで厳かに行なわれる伝統回帰の神前式から、新郎新婦の愛を高らかに謳うチャペルウェディングまで、現代の結婚式は、自分たちらしさを求めてさまざまなかたちをとる。現在につながる様式の結婚式は、文明開化の時代に試行錯誤のすえ創られた。やがて戦争の時代をへて、団塊の世代の支持による神前式隆盛の時代を迎えた。日本人が抱く希望と幸せの変化に応えるように、結婚式は家から飛び出し、神社や教会からもはなれていった。いま、私たちは、なにを願って結婚式を行なうのか。人生の一大事「結婚式」の意味を宗教社会学の立場か捉えなおす。
目次
序章 変わりゆく幸せのかたち
第1章 なぜチャペルウェディングなのか
第2章 結婚式以前
第3章 結婚式の誕生
第4章 神前結婚式の隆盛
第5章 聖性のゆくえ
著者等紹介
石井研士[イシイケンジ]
1954年東京生まれ。東京大学大学院人文科学研究科宗教学・宗教史学専攻博士課程単位取得満期退学。東京大学文学部助手、文化庁宗教課専門職員を歴任。國學院大學神道文化学部教授。博士(宗教学)。現代社会と宗教のかかわりを研究テーマとし、とくに戦後日本人の宗教性の変容の問題を扱う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitam
1
現代では結婚式が成人式に代わる通過儀礼になっている、という論に同感。結婚式には、通過儀礼に不可欠な「苦労」が盛りだくさんだ。仕事の合間を縫って衣装や曲や席順を決める苦労にお金を払うのは、「式を一緒に作り上げて夫婦になる」という意味合いが少なからずあるからだろう。その選択の幅が、業者によって演出された「自由」である一方、多くの人が神前式やキリスト教式などの宗教の作法を重んじるのは、一種の「自由からの逃走」といえるのではないか。オーソライズされた枠組みの中で自分らしさをつくりあげ、人は社会の一員になるのかも。2018/06/14
ことぶき あきら
0
なぜキリスト教挙式なのか。神前式も、戦中戦後の創られた伝統だったんですね。それ以前は人前式だったと。2017/05/13
wyeth2014
0
著者の研究テーマは現代社会と宗教。日本人の宗教性は特殊だと言われるが、現代の儀礼文化においてそれがどう出てくるか。この本では結婚式を分析している。江戸時代までは特定の宗教に関わらずそれぞれの村のやり方で営まれていた結婚式は明治維新頃から変化。契約結婚や神前式が上流階級から広がり出す。太平洋戦争後、神前式が一気に普及。同時に自宅ではなくホテルでの挙式が増加した。やがてバブル期からキリスト教式が主流になり現在に至る。結婚式の歴史もさることながら聖性をどう生活に位置付けるかという問題意識が面白い本。2016/03/26
りの
0
日本における結婚式の歴史、人々の考え方の変遷が分かる。高度経済成長期からキリスト教式やチャペルでの結婚式が急増したことは予想の範囲内だったが、その前に大半を占めていたであろう神前式の歴史が想像よりも短いことに驚いた。明治以前は結婚式に宗教的要素はなく、家と家の繋がりとして行われており、明治時代に大正天皇の結婚式が1901年に神前式で行われたことから神前式が増えたそう。そう考えると神前式が最も多かった時代は100年もないので、意外だった。2022/10/03
ハイザワ
0
日本における神前結婚式の普及過程を追いながら、脱儀礼化が進んだ戦後日本において結婚式が、親から自立するための「擬似的な儀礼」として成立したのではないか、という説が述べられていた。敷衍すると、「ソロハラ」とは儀礼に臨まないものに対する疑似的な共同体からの暴力であるということになる。2021/01/24
-
![天使さんは抗えない~ドSな同期の甘い命令~[ばら売り] 第11話 花とゆめコミックススペシャル](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-2348285.jpg)
- 電子書籍
- 天使さんは抗えない~ドSな同期の甘い命…