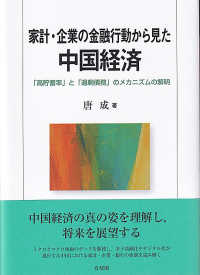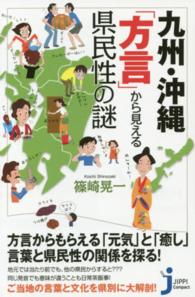出版社内容情報
「きれい好きな」日本の私?
日本人らしさとして語られがちな「毎日風呂に入るのが当たり前」「バスタブでお湯に浸かりたい」という感覚。私たちが無意識に内面化しているこの意識は、いったいどこからきたのだろうか? 西洋人が見た江戸の庶民の入浴習慣から、「日本人は風呂好き」言説のルーツ、家政書で説かれた「清潔な国民」を育てるための女性の役割、さらには教育勅語と関わる国民道徳論で議論された、身体・精神の「潔白性」まで。入浴を通して見えてくる、衛生と統治をめぐる知られざる日本近代史!
内容説明
日本人らしさとしても語られがちな「毎日風呂に入るのが当たり前」という意識。私たちが無意識に内面化しているこの感覚は、いったいどこからきたのか?西洋人が見た江戸の庶民の入浴習慣から「日本人は風呂好き」言説のルーツ、家政書で説かれた女性の役割、さらには教育勅語と関わる国民道徳論で議論された、精神の「潔白性」まで。風呂を通して見えてくる、衛生と統治をめぐる知られざる日本近代史!
目次
第1章 風呂とは古来なんだったのか―前近代の湯屋と西洋のまなざし
第2章 管理・統制される浴場―明治期の湯屋をめぐる風景
第3章 「風呂好きな日本人」の誕生―入浴はなぜ美徳になったのか
第4章 日本の新しい公衆浴場―欧米の公衆浴場運動と日本の入浴問題
第5章 近代日本の新たな「母親」像―家庭衛生から「国民」の創出へ
第6章 精神に求められる清潔さ―国民道徳論と「潔白性」
第7章 世のため国のための身体―国定修身教科書のなかの清潔規範
著者等紹介
川端美季[カワバタミキ]
1980年神奈川県生まれ。立命館大学生存学研究所特別招聘准教授。専門は公衆衛生史。立命館大学先端総合学術研究科修了。博士(学術)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
道楽モン
うえぽん
松本直哉
Sato
さとうしん
-

- 和書
- 英文表現の基本と実際