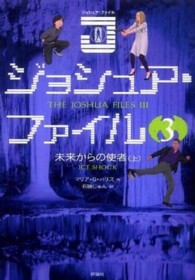内容説明
1920年代のパリで一世を風靡し、日本人画家としてはじめて西洋で成功した藤田嗣治。裸婦画や戦争画、宗教画まで様々な作品を手がけ、今なお毀誉褒貶相半ばする画家は、しかし鮮烈な存在感を残し、その後の美術界に強い影響を及ぼした。没後50年を経た今、「鏡」「線」「色彩」という3つの視点からその作品世界を一望し、そこから“絵画”という芸術表現の見方を導く。
目次
はじめに―日本近代における最大スケールの画家
1部 鏡(フジタの自画像;フジタの戦争画 ほか)
2部 線(極細の線;フジタの裸婦と猫)
3部 色彩(絵画における色彩とは;フジタの宗教画)
おわりに―その後の日本美術
著者等紹介
布施英利[フセヒデト]
1960年生まれ。美術批評家、解剖学者。東京藝術大学美術学部卒業。同大学院博士課程修了(美術解剖学専攻)。学術博士。その後、養老孟司の下で東京大学医学部助手(解剖学)などを経て現在に至る。解剖学と美術が交差する美の理論を探究している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鉄之助
91
藤田は肖像画から始まって肖像画に終わった。芸大の卒業制作から、最晩年、フランスの礼拝堂に描かれたフレスコ画の肖像画。この対比が良かった。「線の画家」とも言われる藤田の原点が、フランスで発見された太古の洞窟壁画に描かれたクロマニヨン人の動物画にあった、というのも興味深い。2018/09/23
春ドーナツ
17
フジタのちょび髭。甥の話。チャップリンから拝借したという。フジダは目立つと思ったそうだ。クールよりもチャーミングな印象を期待したのかな。チャールズ演じる「独裁者」は瓜二つだと思うけれど、なぜちょび髭にしたのか。積年の疑問である。ネットで検索。「ひげ研究所」によると19世紀後半から欧州のセレブ達が好んでいたそうです。滑稽味は喜劇役者に感化された為だった。英語ではハウディという。由来は不明。スペルはhowdyかえ?how do you doを省略したスラング。「オッス」など気軽な挨拶に用いられる。確かに謎だ。2019/01/30
trazom
16
これはいい本だ。「鏡」「線」「色彩」の三つのキーワードでフジタの芸術を分析する構成は大成功。黒田清輝との関係や晩年の宗教画の評価については、著者の見解に異論も感じるが、フジタが、風景画→裸婦→大壁画→戦争画→子どもの絵→宗教画と画風を変化させたこととフジタの人生との関係が、見事に解きほぐされている。また、「鏡」ではモナリザ、「線」ではボッティチェリや日本美術、「色彩」ではラファエロを例にしながら、絵画の基本となる大切なことをさり気なく教えてくれる構成も憎い。「…絵画がわかる」という題名の意味が納得できる。2018/10/09
Francis
12
面白くて2日で読了。藤田嗣治/レオナール・フジタの作品について彼の用いた技法、彼の状況に応じて変わる作風について考察。彼が東京美術学校に行くことを薦めたのは父嗣章から相談された職場の上司森林太郎、すなわち文豪森鴎外だったことには驚き。芸術家は芸術家を知るのですね。2018/08/22
anco
9
藤田嗣治展に行く前に読みました。藤田嗣治の生涯や作品の背景などを知ることができました。2018/11/22
-
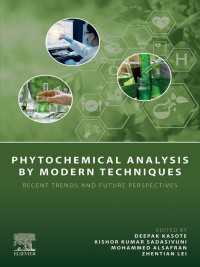
- 洋書電子書籍
- Phytochemical Analy…
-

- 電子書籍
- VTuberなんだが配信切り忘れたら伝…
-
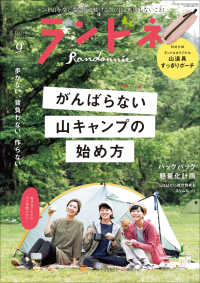
- 電子書籍
- ランドネ 2022年9月号 No.125
-
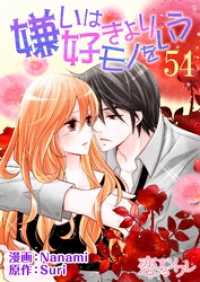
- 電子書籍
- 嫌いは好きよりモノをいう(フルカラー)…