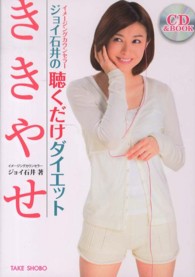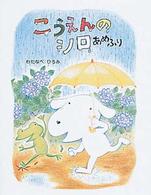内容説明
市場経済とIT化が急速に進む中国では、三億人といわれる中産階級たちがスマホで世界中の情報と商品を手に入れ、スクープやスキャンダルに夢中になり、アリババなどの巨大IT企業を支えている。SARSから天津爆発事故まで社会を揺るがした大事件を織り込みつつ、「中国の報道はプロパガンダ一色」という色眼鏡越しでは見えてこない現代中国のダイナミズムを伝える。
目次
序章 プロパガンダメディアの変遷
第1章 「中産階級」がつくる新しい時代
第2章 情報統制の限界
第3章 メディアの市場化と権利意識の目覚め
第4章 海外情報の影響・経済メディアの活躍
第5章 「つながり」から「社会参加」へ
第6章 SNSがつなが記憶と人々
第7章 狙い撃ちされた知識人とメディア
第8章 スマホが書き換えたメディア地図
第9章 巨大企業は味方か敵か
著者等紹介
ふるまいよしこ[フルマイヨシコ]
フリーランスライター。1987年北九州大学外国語学部中国語学科卒業。1989年香港中文大学で広東語を学んだ後、現地で雑誌編集者を経て独立。香港に14年、北京に13年半暮らし、日本では報道されない現地の社会事情を日本のメディアに寄稿。2015年4月にいったん帰国。日中の認識のズレにポイントを置きながら中国事情の分析を発信している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
70
2016年発行で中国ITメディアがまだ元気な頃の著作。その為著者がまだ中国メディアの未来を信じれていたのが、今となっては痛々しい。現在から見ると香港のリンゴ日報は跡形もなくなり、アリババはジャック・マーがえらい事になってるし、テンセントもゲーム規制で大ダメージ受けようとしてるし…。最近社会を完全に統制下に収めようとしている中国政府の政策見ていると、本書に書かれているメディア対政府は完全に終焉を迎えようとしているように思える。そういう意味では、本書は時代を記録するのに適した時期に書かれたようにも思える。2021/10/19
Kentaro
27
中国は国内において、自国民が外国メディアの記者として働くことを禁止している。だが、外国人では取材の時に言葉や習慣の障壁があったり、姿か立ちといった外見の違いから満足な取材が行えない事が多い。 そんなときに中秘と呼ばれる中国人秘書の協力者を使ってインタビューやアポとりを行う。 表向きは記者ではないが、中秘の協力なしに西洋メディアの中国報道は不可能だという。 彼ら自身はジャーナリスト志望であるために、面白そうな情報をネットやSNSから軽々と拾い上げ、中国メディアが忖度して取り上げられないネタを見つけてくる。2019/07/04
hk
16
こういうことなんじゃないかなあ。……中国では共産党のメディア規制は極めて強固だ。だが中産階級以上は世界を股にかけビジネスをしている以上、海外情勢を熟知する必要がある。なぜならそれが中国経済の発展につながるからだ。わけても天安門事件以降は経済成長が共産党の命綱であるから、中共としても海外情勢を中産階級に届けなければならない。ここに政権維持のため言論統制を敷きたい中共と、経済成長のために海外情勢を国内に供給したい中共という二面性が浮かびあがる。この相克する命題に中共がどのように対処しているのかを考察したい……2019/06/09
ののまる
9
「微博」(中国版Twitter)が実名登録制になり締め付けが強くなってきた今、中産階級と政府の情報攻防戦はどうなっていくのかな、と思っていたので、読み応えあった。2016/06/26
マネコ
8
中国当局による情報統制とメディア側の攻防について大変興味深く読めました。中国では国防費より治安維持費が多く、外部より内部の崩壊を不安に思っています。ジャーナリストは圧力と低賃金にたえながら、さまざな不正を糾弾し、民衆に情報提供するという点で尊敬します。これからも悪いことは悪いといえるように、たくましく活動してほしいです2019/10/26