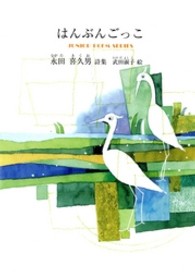内容説明
世の中には難しい出来事があふれ、それを伝えるメディアの言葉も難解だ。障壁だらけの現代社会で、そうした情報を誰にもわかりやすく伝える表現とは何か。本書は、新聞記者と知的障害者が、ともに取材・執筆・編集に挑戦する新聞「ステージ」の知恵と工夫を紹介。難しい記事をわかりやすく書き、表現する試行錯誤を通して、新しいコミュニケーションを考察する、画期的な「バリアフリー文章流儀」入門。
目次
第1章 やさしい記事・難しい記事(「ステージ」誕生;O157 ほか)
第2章 わかりやすさの技法(長いと難しくなる;主語と述語の微妙な関係 ほか)
第3章 迷路のような社会(新聞語;比喩 ほか)
第4章 障害とコミュニケーション(知的障害者の文章;メモリー ほか)
第5章 ドラマから裁判まで―バリアを解く(「聖者の行進」を見に行く;アルジャーノンに花束を ほか)
著者等紹介
野沢和弘[ノザワカズヒロ]
毎日新聞東京本社社会部副部長。1959年静岡県熱海市生まれ。毎日新聞入社後、厚生省(当時)、障害者虐待取材班、児童虐待取材班などを担当。科学環境部副部長を経て現職。また社会福祉法人「全日本手をつなぐ育成会」理事・権利擁護委員長、千葉県障害者差別をなくす研究会座長などを歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
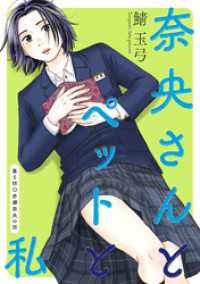
- 電子書籍
- 奈央さんとペットと私 分冊版 5 アク…
-

- 和書
- 野菜