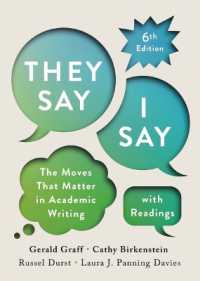内容説明
平安時代は、紫式部の先輩にあたる歌人で『栄花物語』の作者と考えられている赤染衛門、少し年上のライバルで『枕草子』を書いた清少納言、恋多き情熱の歌人である和泉式部などの女性の名前が思い起こされる時代である。では、なぜ彼女たちは、世界的な遺産ともいうべきすばらしい文学をのこすことができたのだろうか。また、なにに悩み、なにを考え、どのように生活していたのだろうか。本書では主として、平安京で生活した女性たちの結婚や子育て、働き、教養、老後などをさまざまな角度から眺めてみた。
目次
序章 『源氏物語』の時代
第1章 愛と結婚
第2章 住まいと家族
第3章 出産と子育て
第4章 働く女たち
第5章 女の経済生活
第6章 文化の創造
第7章 旅する女たち
第8章 病と出家・死
終章 家の成立と女性
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
びっぐすとん
13
再読。平安時代の妻の務めは使用人の管理、衣装(染物、仕立て)の用意、子供を産むこと。しかし妻の立場の不安定さは女性として心許ない。次妻以下や妾は勿論、正妻であっても安穏としていられない。子供や頼りに出来る兄弟等がいないと上流貴族の娘でさえ妾や女房に落ちぶれて、野垂れ死になんてこともある。『源氏物語』でも末摘花とか空蝉なんて光源氏が庇護しなければ野垂れ死にかも。槿の君とか朧月夜も親が死んだ後は寂しい暮らしのようだし、出家後の生活費はどうしていたのか?女にとってこの世は苦界。玉の輿に乗れたのは10世紀まで。2020/06/01
びっぐすとん
7
108円本。服藤さんの著作は何冊か読んでいるので、目新しさはなかったが、かねてから平安時代のお墓ってあまり聞かないし、『源氏物語』でも葵の上や紫の上が死んで大泣きしていた光源氏なのに墓参りにいくシーンとかないけど、荼毘に付した後どうなってるのかな?と思っていたので、当時はまだ墓参りという風習が一般的じゃなかったことや夫婦でもそれぞれの実家の墓所に納骨されたこと、庶民にいたっては野ざらしだったとか、その辺がわかってスッキリした。2017/08/21
takao
2
ふむ2024/09/03
ひだり
2
大河ドラマ「光る君へ」の参考書として。平安時代の結婚や出産、仕事のことがよく分かる。時折、大河ドラマに出てくる人物のエピソードも出てきて、「あぁ、あの人ね」とニヤリ。藤原実資の日記に「ああ嘆息、嘆息」って書かれてて、ロバート秋山さんのお顔が浮かぶ(笑)2024/02/22
cinnamon
1
大河ドラマに登場しているあの人たちがたくさん紹介されており、楽しく読めた。 大河ドラマの頃が女性たちがまだ表舞台で自由に活躍出来た最後の時代なのか。これ以降女性たちは家制度に縛られていく。院政期以降に文学の面で名を残した女性はほとんどいない。政治面では悪女と言われるし。 この、長く続いて来た抑圧が今の私たちを知らず知らずの内に縛り付けている。これだけ長く続いて来たものだからすぐとは行かないが少しずつ変えていくしかないのだろうな 2024/03/14
-

- 和書
- 心の疲れをとるコツ
-

- 電子書籍
- 百花園 第二三〇号 百花園