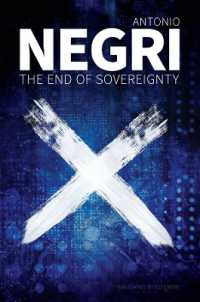出版社内容情報
答えは誰かがくれるものじゃない。自分で見つけるものなんだ。
進むべき道に迷ったとき、先が見えずに苦しいとき、生きがいを見失ったとき、言葉が君を支えてくれる。「おもう」「分かる」「考える」「読む」「書く」「聞く」「話す」――素朴な動詞の意味を問いながら、大切な言葉と出会う7つの授業 。生誕60周年を迎える池田晶子の傑作『14歳の君へ どう考えどう生きるか』へのオマージュを込めた、新しい「人生の教科書」。
内容説明
進むべき道に迷ったとき、生きがいを見失ったとき、君を支える言葉と出会う「7つの授業」。
目次
おもう
考える
分かる
読むと書く
対話する
著者等紹介
若松英輔[ワカマツエイスケ]
1968年新潟県生まれ。批評家、随筆家。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。慶應義塾大学文学部仏文科卒業。2007年「越知保夫とその時代 求道の文学」にて第14回三田文学新人賞評論部門当選、2016年『叡知の詩学 小林秀雄と井筒俊彦』(慶應義塾大学出版会)にて第2回西脇順三郎学術賞、2018年『詩集 見えない涙』(亜紀書房)にて第33回詩歌文学館賞詩部門、『小林秀雄 美しい花』(文藝春秋)にて第16回角川財団学芸賞、2019年に第十六回蓮如賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
81
若松さんが中学三年生に行った授業を記録した一冊。池田晶子、小林秀雄、リルケ、田中美知太郎、キューブラー=ロス、ピカートらの文章を土台にして、「おもう」「考える」「分かる」「読むと書く」「対話する」と講義が進む。思う・考える・分かる・読むまでは、一人の個人の内的行為として納得するが、その後、誰かに書き、誰かと対話することの意味をどう位置付けるかが難しい。まして、最終章で議論される「沈黙と対話」は、一見するとアンチノミーであり、私自身、十分に納得したと言える自信がない。14歳の中学生は、どう感じたのだろう。2020/12/30
ネギっ子gen
40
筑波大学付属中学校で行われた講義を基に書き下ろし。「おわりに」より。<人はもっとも深く考えていることは言葉になりませんから、発言しない人に問いがないのではありません。むしろ、この本の「いのち」は、生徒たちの言葉にならないおもいと苦しみなのかもしれません。真摯に生きるものは、その瞬間に苦しみを背負うことになります。もちろん、苦しみだけでなく、朽ちることのない喜びや自分であることの誇りも同時にわが身に宿します。こうした目に見えない若者たちの人生との格闘は、私にどれほど大きな影響を与えたかもしれません>と。 ⇒2020/11/24
しょうじ@創作「熾火」執筆中。
30
【1回め】この本は、若松さん自らが「特別な一冊」と言っている。確かにそうなのだ。人は、書き得ないこと、語り得ないこととして、沈黙を選ぶことがあるが、むしろそのことによって、人と人とはつながり得ることさえあることを静かに語っている。これらの言葉は、例えば池田晶子や小林秀雄などを経由して語られているが、「私」の中に、既に(あるいは、遂に)語られてこなかった「コトバ」として「あった」ものかもしれない。『14歳の教室』という標題に惑わされることなく、広く手にされてほしいと思う。2020/07/31
しょうじ@創作「熾火」執筆中。
26
【2回目】読書会で紹介するために、傍線を引いた部分をピックアップして読了とする。若松さんの著作には、何冊か触れてきたが、何となく言わんとしていることが分かってきたように思う。識り得ないことを識り、語り得ないことを語ろうとすること。読む「と」書くということ。仏教には「不二」という考え方があるのだが、対立項と見えることが、実のところ相即の関係であることに通じているのではないかと考えてみた。2020/12/26
ほし
17
若松さんが実際に中学校で行われた授業をもとにして書かれた本。池田晶子や小林秀雄、リルケなどのことばを引用しながら、おもうこと、考えること、読むことや書くことなどについて語っています。文章としてはとても優しく書かれているのですが、その内容はとても深く、容易に飲み込めるようなものではありません。言葉にならない言葉、時間を超えた時の世界、沈黙によってなされる対話など、深く人生を生き抜くことで、はじめて分かり始めるような内容が延べられています。大人にも、というより日々を慌ただしく生きる大人にこそ勧めたい一冊です。2020/09/25