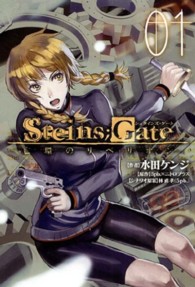内容説明
「ネット選挙」が解禁するも、投票率が上がらない時代。しかし、インターネットをツールとした政治の透明化に向け、市民も行政もすでに動か出している。情報社会論と公共政策学を専門とする著者が、従来の直接民主主義/間接民主主義の対立を越えた、「ネット選挙」以後に目指すべきこれからの「民主主義」を描き出す!
目次
第1章 ネット選挙解禁と、二〇一三年参議院選挙(公職選挙法とネット選挙―公職選挙法の理念/ネット「だけ」解禁;理念なき解禁―政治コスト低下という言説/韓国の先行事例;前哨戦としての二〇一三年東京都議会議員選挙―ネット選挙の先取り合戦/通常化か、平準化か ほか)
第2章 なぜ選挙に情報技術を導入するのか―民主主義の理想、あるいはデジタル・デモクラシーを求めて(「ネット選挙解禁」に残された課題と展望―競合する政治の透明化と政治マーケティングの高度化;政策論争の不在と双方向性の問い―政党と候補者の力学;マスメディアとネットメディアの影響力―衆人環視状況の改善ネットで発信せざるをえなくなった政党・政治家 ほか)
第3章 「行政の情報化」と「政党の情報化」(「行政の情報化」に向けて;日本版オープンガバメント―二〇〇〇年代中盤以降の海外事例日本国内の試み;アイディアの“もと”を政策へ―「開かれた行政」の今 経産省「オープンガバメントラボ」 ほか)
付章 海外レポート 広がるデジタル・デモクラシーの波―ドイツ海賊党の光と影
著者等紹介
西田亮介[ニシダリョウスケ]
1983年京都生まれ。立命館大学大学院先端総合学術研究科特別招聘准教授(有期)。専門は情報社会論と公共政策学。情報と政治、ソーシャルビジネス、協働推進、地域産業振興等を主な研究テーマとする(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
takizawa
ophiuchi
Makoto Osawa
サイトトウロク
-

- 電子書籍
- 語らいサンドイッチ 角川文庫
-
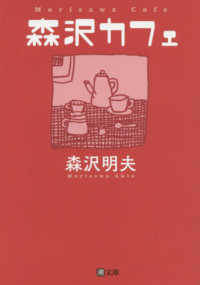
- 和書
- 森沢カフェ 潮文庫