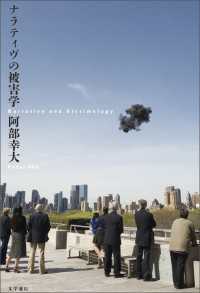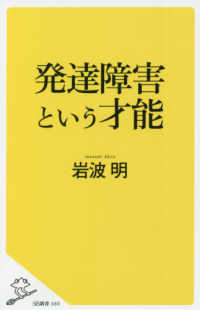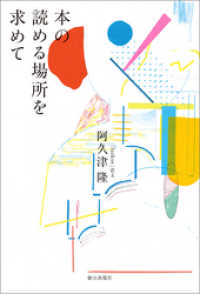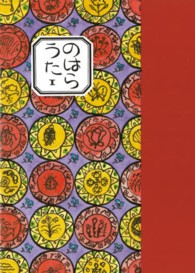内容説明
大戦後の世界で大いなる発展をとげたアメリカと日本―第一次世界大戦への参戦(1914年)、ポーツマス条約(1905年)、三国干渉(1895年)、鹿鳴館外交の開始(1883年)。外交リアリズムを追求した「帝国外交の時代」をたどる。
目次
第1章 誤算の第一次世界大戦―第一次世界大戦に列強が没頭するなか、日本は大陸権益の拡大に邁進する。その結果、米中との関係は難しくなった。
第2章 日露戦争薄氷の総力戦―ポーツマス条約で戦勝国の地位を得た日本。それを導いたのは外交と軍事が一体となった政治のリーダーシップだった。
第3章 日清戦争三国干渉の“教訓”―三国干渉によって、遼東半島を返還させられた日本は、その挫折から、あらためて富国強兵路線を強化することになる。
第4章 鹿鳴館欧化からナショナリズムへ―鹿鳴館に象徴される急速な西洋化によって、政府は条約改正をめざす。しかしそれは国内のナショナリズムを強く刺激する。
著者等紹介
北岡伸一[キタオカシンイチ]
1948年奈良県生まれ。政策研究大学院大学教授、国際大学学長、東京大学名誉教授。東京大学法学部卒業。同大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。法学博士。東京大学法学部教授、国連代表部次席大使などを経て、2012年より現職。専門は日本政治外交史。主な著書に『自民党―政権党の38年』(中公文庫、吉野作造賞)など多数。2011年、紫綬褒章受章(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ごる
果てなき冒険たまこ
yasu7777
YayoiM
cochou