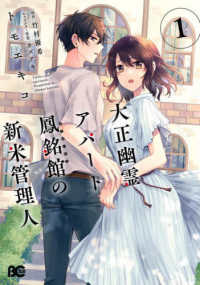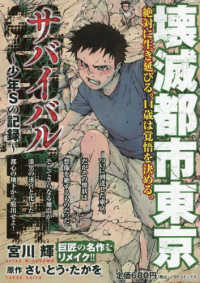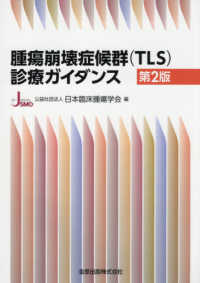内容説明
8頭の種牡馬から読み解く名馬誕生の秘密。「JRA馬事文化賞」受賞のロングセラー。
目次
第1章 血の宿命―革命の使者セントサイモン
第2章 約束の血―影の立役者ハイペリオン
第3章 血の盲点―近代サラブレッドの祖ネアルコ
第4章 喧しい血―偉大なる後継者ナスルーラ
第5章 辺境の血―サラブレッドの新種ノーザンダンサー
第6章 新しい血―雑草血統の選りすぐりネイティヴダンサー
第7章 稀少の血―日本に息づくトウルビヨン
第8章 血の相性―眠りから醒めたロイヤルチャージャー
著者等紹介
吉沢譲治[ヨシザワジョウジ]
1955年、愛媛県生まれ。早稲田大学政経学部中退。血統評論家、ノンフィクションライター。月刊誌、週刊誌の記者を経てフリーに。JRA日本中央競馬会の月刊誌『優駿』で、重賞優勝馬の血統ページを担当して四半世紀以上になる。かたわら同誌を含めた雑誌に血統記事、ノンフィクション、連載コラムを執筆。『競馬の血統学―サラブレッドの進化と限界』で、1998年度JRA馬事文化賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゲオルギオ・ハーン
26
競馬の血統について海外も含めた長い歴史を書きつつ、血統に革命を起す要因も考察した一冊。血統で全てが決まるならば、イギリスの純血戦略(3ー4世代前が同じ名馬で交配)が続くべきだが、実際はそこまで単純ではない。イタリアから当時の最強馬ネアルコを送り出したフェデリコ・テシオによれば近親交配という『人間の間違いは自然によって抑制・排除される』近親交配は傑作が生まれることもあるが、ほぼ大失敗するということを表現している。実際、イギリスの血統主義はイタリア、アメリカ、フランス、日本の馬たちの前に敗れていくこととなる。2022/12/22
futabakouji2
8
名馬の生産は他人の生産に結果的に貢献する。というのも、1頭の名馬が大成功したら、その馬に人々が群がる。最初は皆でフィーバー。そのフィーバーはノーザンダンサーであり、セントサイモンであった。今ならディープインパクトだろうか?その馬の血が全国に広がり、同じ血統背景を持つ馬ばかりになって、血統の袋小路になる危険性がある。おまけに名馬のオーナーならもう配合ができないで破産することもある。飽くなき名誉を追い求めて、結局他の生産者に貢献する競走馬生産に寂しさを感じた。2018/06/26
おーしつ
8
人為的に閉じられた遺伝子の中で配合が行われているサラブレッド。 圧倒的な能力を持った種牡馬がやがて「血統の飽和」「血統の袋小路」に行き詰まり、「傍流血統」「雑草血統」が世界の勢力図を書き換えるという歴史が(例えばグローバル化や早熟・スピード志向へのシフトなど競馬観の遷移などのファクターもあるが)繰り返されている事実。 おそらく関係者は皆、頭では分かってはいても、資金や偶然が支配する世界の中でそこから抜け出せないのだろう。 血のロマンは、血の呪いでもあるのだな。 続編(母系編)や「血のジレンマ」も読みます。2012/07/25
きっち
5
面白くて一気読み。サラブレッドの歴史の白眉は、長きにわたる近親交配により血統の袋小路に陥っていたイギリスに、競馬後進国のアメリカ(と、イギリスは見下していた)が、血統の曖昧な馬で殴り込みをかけ、お高くとまっていたイギリスを屈服させてしまうところだなあ。血統の曖昧な馬の存在を認めているじてんで(日本にもかつてサラ系というのがいた)サラブレットの純潔性はなくなってるんだから、もういちど東洋種の血を入れた方が良いように思うが。競馬をやらない人にはチンプンカンプンの本かも知れないが、興味のある人はぜひ。2019/04/01
ベンチャーナイン
3
サンデーサイレンスは良くも悪くも日本の勢力図を大きく変えたというのは紛れも無い事実。サンデーの血を蔓延させないように海外から種牡馬を連れてくるという悪循環に繋がって、内国産での発展がなかなか進まないっていのも納得。その中で産まれた三冠馬オルフェーヴルの母父メジロマックイーンの美しさが魅力的だし、競馬は改めてロマンだなと実感させられた。2012/08/14