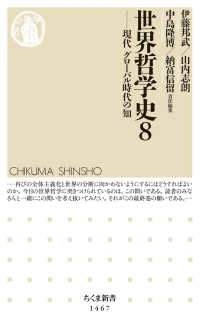内容説明
“編集”の視点で読み解く、まったく新しい法然の世界、これがセイゴオ流、法然入門。
目次
第1部 法然の選択思想をよむ(忘れられた仏教者;専修念仏への道;法然のパサージュ;「選択」の波紋)
第2部 絵伝と写真が語る法然ドラマ(法然生誕の地;突然の夜討ち;時国の遺言;比叡山入山;宝ヶ池越しに比叡山を望む;18歳での遁世;浄土信仰の象徴;一向念仏に帰す;吉水での説法;念仏発祥の地;善導との夢中対面;大原問答;大原問答の地;苦情兼実の帰依;僧兵の計画;弟子の死罪;遊女教化;法然の臨終;法然の眠る場所)
第3部 特別対談 松岡正剛×町田宗鳳―3・11と法然(大震災を経て;辺境から生まれる希望;仏教の土着化;日本仏教の系譜;仏教とイメージ;法然の引き算;仏教を再統合する;「悪人」とは誰か;仏教における死)
著者等紹介
松岡正剛[マツオカセイゴウ]
1944年、京都生まれ。71年に工作舎を設立してオブジェマガジン『遊』を創刊。工作舎を退社後、東京大学客員教授、帝塚山学院大学教授を経て、現在は編集工学研究所所長、イシス編集学校校長。情報文化と情報技術をつなぐ研究開発プロジェクトに携わる。日本文化研究の第一人者として、「連塾」などの私塾を多数開催。09年より、丸善・丸の内本店4階に全く新しい書店「松丸本舗」をプロデュース(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
うりぼう
39
昨年秋、松丸本舗で購入。法然は古今の経典を読破する中から、南無阿弥陀仏と唱えることで極楽往生できるという易行に到達する。それは、他を捨てたのではなく、重ね合わせ編集した結果。その確固たる自信が、他派からの批判に臆せず、他派を批判せず、高木氏の地球村の「非対立」のようだ。第2部の絵伝と写真の法然ドラマがその時代を写しつつ面白い。第3部の町田氏との対談は、東日本大震災が、法然の時代の末法と重ねられ、日本文化の祖型が「追放と復活」であり、辺境の地から新たな胎動を期待。「生死を離れ」十牛図の痴聖人が理想的人間像。2012/03/20
おせきはん
12
南無阿弥陀仏と唱えることで極楽往生できるとし、仏教を貴族のためのものから庶民のためのものへと転換させた法然の「編集力」について語られています。米国における反知性主義の台頭に近いものがあると感じました。2018/01/16
非日常口
3
松丸本舗は色々ときっかけを与えてくれた。あのシステムが他に受け継がれれることはあるだろうが、気づける人はどれだけいるだろうか。ノマドと言う言葉がビジネスの世界で非常に雑に扱われる中、この本は読み手に様々な思考に楔を打つだろう。そう、内容はあえて書くまい。一行に込めたモノに触れるのはあなたの物語から紡がれるのだから。2012/10/02
bookthinker
2
10年くらい前に読んだ本。 その時は親鸞上人と松岡正剛氏の全方位型の教養への興味から手に取った。したがって、法然上人にはさして関心はなかった。本を読み終えたあとも、ふーん。としか思ってなかった気がする。今更、法然さん、凄まじいクリエイターだなと気づかされた。 しかし、最近延暦寺に行って、天台宗を目にして思うに、修行は無価値かというとそうでもないのではないか。極楽浄土へのアプローチの仕方が浄土宗及び浄土真宗と天台宗とで異なるということなのかなと考えた。 天台宗の勉強を終えたら改めて再読することに決めた。2021/03/12
Yoshihiro Yamamoto
2
A+ 第3部の町田宗鳳氏との対談は特に秀逸。著者は、「法然が専心念仏にたどり着いたのは、膨大な読書量の中からのスクリーニングによってで、その際、引き算はしているが、捨て去るのではなく止揚している」と解く。町田氏は、文明国には「文化の祖型」があり、日本は「追放と復活(蘇り)」…スサノオ、大国主命、大海人皇子など。また、法然以前は「三宝を篤く敬えば救われ」たが、それが出来るのは貴族階級だけ。法然は「南無阿弥陀仏」と称えると誰もが極楽浄土に行けるとして宗教革命(仏教の土着化)を起こし「成仏の条件」を取っ払った。2013/01/27