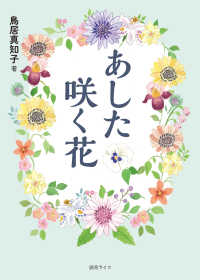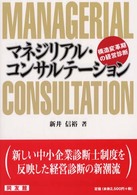内容説明
「68+57=5」は間違っていない。「+」という記号が「プラス」という概念を表すことの根拠は何か?現代の言語哲学をリードするクリプキとともに、ことばや記号に内在するパラドクスを解きほぐす。
目次
第1章 グルー(ひとがふだんしている推論の多くは帰納法である;「グルー」が登場する ほか)
第2章 クワス算(「68+57」の正しい答えは「5」である!;同じ話を「グルー」について繰り返してみる ほか)
第3章 懐疑的解決(実際のところ、どれだけ困ったことになっているのだろうか;意味について語ることをやめようという人もいる ほか)
第4章 ウィトゲンシュタイン(懐疑的議論と懐疑的解決はウィトゲンシュタインの議論と解決だとクリプキは言う;私的言語論は懐疑的解決の一部である ほか)
著者等紹介
飯田隆[イイダタカシ]
1948年北海道札幌市生まれ。東京大学大学院人文科学研究科(哲学専攻)博士課程中退。専攻は言語哲学、数学の哲学。現在、慶応義塾大学文学部教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
夜間飛行
185
私が今まで56以下の足し算しかやったことがないとして、68+57を125と答える。すると《57以上の+の答は全て5になる》という意味で+を使う人から「5が正しい」と言われる。クリプキ曰く、私が私の意味で+を使っていることを(57以上の+をやったことのない)私は証明できないのだと。何て奇妙なことをいうのだろう。私の心の問題に、なぜ証明が必要? 著者はクリプキの問いを《人はどうして自分の心を知りうるのか》と言い換える。この問いはウィトゲンシュタインの私的言語の話と繋がって、俄に面白くなるが、やはり難しかった。2021/07/18
hakootoko
9
問いと答えの間にカテゴリーの共有がない問答には意味がない。「何色か」がどんなカテゴリーを問うのか、意味が決まるのは歴史や生活形式であると言ってもいいけど、まぁ、つまりはときどきの状況に対する動機を共有すれば、言葉を同じ意味で使うようになるのではないか。動機が共有できないなら話をしても意味はない。どんな問いにも人間はどういうことを気にかけるのかという暗黙の儀礼が潜んでいる。クリプケンシュタインは宇宙人のように社会を観察しているけど、ウィトゲンシュタインは人間が誤解によって宇宙人めくことを笑うって感じかな。2023/07/25
H2A
8
読み終わってから、増補版があることを知ったのでそれも読むつもり。2022/07/18
りっとう ゆき
5
なんかわたしの勝手なイメージだけど、すごくひろーい曖昧な場所のほんの一部で私たちは、とりあえず感じ取れた経験をもとにいいように意味づけたりして仮に生きてるようなイメージ。とりあえず今までこうだったからまたこうだろうという暗黙の取り決めの中で。言葉に関しても、絶対じゃないことは明白(例えばある哲学者の思想の解釈1つとっても人それぞれ)だけど、使わなくてはいけないのだから曖昧なりに確かめ合いながら使うしかないのでは。2021/11/03
ヘンリー八世が馬上試合で死んだことは内緒
5
違うんだな―、お前が今までやってきたことは実はプラスじゃなくてクワスだったんだよ!お前が今まで見てきた色はブルーじゃなくてグル―だったんだよ!お前が今まで考えていると思っているのはくわぁんがえているだったんだよ!お前が毎週見ていたものはけいおん!じゃなくてきぇいおん!だったんだよ!!!!!そーなのかーぁぁぁぁぁぁあああ!!!!わたしはいままでなにをやっていたんだよぉぉぉおおおお!助けてクリプキさん!!!クリプキ「俺のスリッパはどこだぁあぁぁぁぁぁぁぁぁぁlっぁぁあっぁぁぁぁあ!」2013/02/14