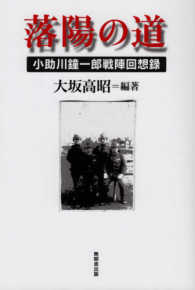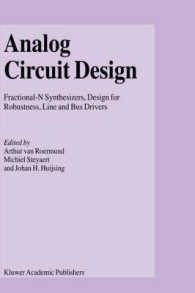内容説明
稲作が伝わる以前の縄文時代、わが国に「農耕」と呼びうるものは存在したのか。作物はいかにして意図的に栽培されるに至ったのか―。先史農耕の痕跡に科学的分析を加えた最新の成果に立脚し、学際的な視野から畑作農耕の成立と展開を探る。
目次
序章 日本における畑作農耕の成立をめぐって
第1部 バイオ・アーケオロジーからの接近(縄文時代の環境と生業―花粉分析の結果から;古代のイネ科植生;電子顕微鏡でみる縄文時代の栽培植物)
第2部 作物と雑草をめぐる諸問題(野菜の系譜―地方品種の来た道;ソバの系統とその起源を探る;ヒエ・アワ畑の雑草;雑穀の栽培と調理)
第3部 日本の基層文化との関連(シベリアの先史農耕と日本への影響;縄文人の生業―その生態的類型と季節的展開;縄文文化の成熟と植物栽培の意味;稲わらと植物繊維―稲作以前の植物利用を復元する;「ハタ」と「ハタケ」―地域差と信仰;先農耕段階とその類型―農耕起源論と関連して;総合討論 縄文の畑作農耕とその検証の可能性をめぐって)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
8
「ウサギの被害は、それが多いところでは絶望的にマメ類を荒らす。収穫期にも決して劣ることはない。ウサギの天敵はキツネだから…稲荷神の使者、つまり農神のつかわしめとして尊敬をうけたのは、あるいはネズミやウサギをやっつけて初期の畑作農民の味方であったからではなかろうか、と思うほどウサギは数多ければ畑作の大敵であったらしい。…古代に人類と競合・対立した鳥獣は、多くの農民にとってきわめて日常的な存在であるとともに、その動向や性格は重要な関心事であった。多くの口承文芸にも彼ら鳥獣の登場することは必然的であった」2022/05/01