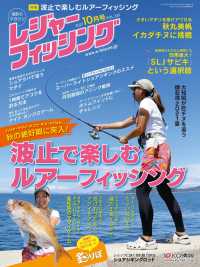内容説明
時代の激動期に生きた最後の大物絵師がいた。国芳に美人画を学び、狩野派を僅か19歳で卒業した天才絵師、暁斎である。骸骨や動物を人間の如く描きだす筆致にお雇い外国人も驚嘆した。徳川・明治と時の政府を笑い飛ばし、文明開化に右往左往する世情を面白おかしく描き常に庶民に温かい目を向けた。まさに時代の寵児と言える画狂人の生涯を変転する時代とともに鮮やかに描きだす。
目次
序章 世界を流転した代表作「大和美人図屏風」
第1章 幕末の美術界―浮世絵は衰退していたのか
第2章 生首を写生する少年絵師
第3章 パリ万国博覧会と印象派の画家たち
第4章 世界が注目した未知の大画家
第5章 北斎と暁斎―なぜヨーロッパに受け入れられたのか
第6章 暁斎の戯画―時代へのまなざし
第7章 開化に翻弄された明治期の美術界
第8章 明治の絵師暁斎の世界
第9章 人類の遺産となった日本美術
付章 絵日記に見る暁斎の日々の暮らし
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ミネ吉
12
河鍋暁斎の業績を、江戸末期から明治初期の時代背景と共に紹介する書籍。澤田瞳子さんの「星落ちて、なお」から流れてきたが、面白かった。よくわかったのは暁斎の天才ぶり。子供のころから頭角を表し、呼吸でもするかのようにどんな画題でも描くことができた。明治維新で世間の価値観が反転し、当時の画家たちが絵画の近代化に苦心するなか、暁斎本人は動ずることなく当時の世相も含めただ絵を描き続けていたようだ。特に戯画は秀逸で今見ても笑える。文明開化を茶化して河童が教室で「しりこたま」のローマ字を教えている絵とかかなり好き。2025/02/21
みこと
10
面白かった。読むのに少し時間はかかったけどどうしても挫折できなくてなんとか読了しました。それにしても幕末〜明治にかけてこんなにすごい絵師がいたとは。狩野派の流れを汲み浮世絵も肉筆画も描き、変貌していく世の中を静かに観察しひたすら描いた暁斎。あまり国内で知られてないのはその作品のほとんどが当時から世界に流れ出ていったから。今見てもそのデッサン力、描写力がずば抜けていると思う。未だ把握し切れていない江戸の浮世絵が世界に何千点も存在しているなんて信じられますか⁇ これは…読んで良かった!一度、生で見てみたい。2019/01/09
ぼたん
2
明治初期の浮世絵を取り巻く環境と暁斎についての本人。狩野派の絵師としての伝統を受け継ぎ浮世絵師としても活躍し様々なジャンルを書いた絵師。過去にとらわれていた美人画から脱却した美人画を作り上げた。文明開化を冷静に見つめて風刺画を描く。2012/07/01
かねかね
2
国芳の弟子だったよね? とのことで読み始めましたが、暁斎自身にかなり興味が湧きました。収録されている絵は本当に巧い! 外国人の弟子がいたりとかもするし。とても面白く読みましたよ。2010/05/09
果てなき冒険たまこ
1
幕末から明治初期にかけての日本美術空白期にただ1人時代に左右されることなくありとあらゆるものを描き続けた河鍋暁斎。その業績を日本という側面からだけではなく欧州でのジャポニズムと絡めて紹介する良本。中国美術の模写から始まった日本美術は浮世絵師たちが現れるまではその呪縛からは抜けられなかったということか。江戸期以前の絵画は芸術的なんだろうけどなんかつまんないなと思ってたんだよね。この次は日本美術史を勉強せねばならんな。あとはジャポニズムだな。2022/04/15