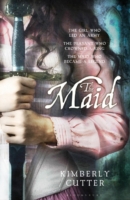内容説明
音楽はバッハやヘンデルから始まる、と思われていたのはそう遠い昔のことではない。あの爽やかなヴィヴァルディの「四季」が鳴り響いたのは、昭和30年代であった。バロック音楽があるという発見は、人びとに生きる力と喜びを与えた。そして1980年代のいま、バロック音楽の生まれたままの響きを再現しようとする試みが盛んである。バロック音楽とは何か。その全貌と今日的意義を解く。著者は教会音楽やバッハの研究ですぐれた業績をあげ、第1回辻荘一賞を受けた(1988年)気鋭の音楽美学者である。
目次
1 装いに真実を求めて―バロック音楽の始まり
2 音楽による祝祭―オペラの誕生
3 この世における聖の開花―宗教音楽の高揚
4 廃墟に流れる歌―ドイツ音楽の目覚めと発展
5 歌うヴァイオリン―イタリアにおける器楽の興隆
6 大御代を輝かす楽の音―フランス音楽の1世紀
7 趣味さまざま―国民様式の対立と和合
8 音楽を消費する先進行―イギリスとヘンデル
9 神と人間に注ぐ愛―バッハにみるバロック音楽の深まり
10 数を数える魂―バロック音楽の思想
11 コーヒーを飲みながら、音楽を―18世紀における音楽の市民化
12 現代に息づくバロック―受容史と今日的意義
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
内島菫
20
ライプニッツが音楽を「魂が知らずしらずのうちに数を数えること」と規定しているのが面白い。また、「ある音楽がある情念を聴き手の心に呼び起こすことが出来るのは、音楽と人間の心に、一定の数学的比例が共有されるためであるという。バロック時代においては、感情表現とかかわらせる形で、音楽の数学的性質が指摘される。さまざまな存在の原理である数は、当時、感情の原理でもあったのである」とするキルヒャーの音楽による情念論をもっと知りたくなった。バロック時代は、今から見ればまだ素朴であるとはいえ、2020/04/22
松本直哉
15
整数倍の周波数の音程に基づく純正律の透明な響きを捨てて、響きは濁っていても転調などに融通のきく平均律を選ぶバロック音楽の動きに、同時代の天文学の、完全な円というドグマを捨てて、惑星の楕円軌道を提唱するケプラーの仕事が重ね合わされているところを興味深く読んだ。古代ギリシャ哲学以来の数学的均斉への憧れからの解放。不均一なもの、歪んだもの、割り切れないものへの嗜好。戦争と飢饉と疫病に喘いだ17世紀は「きれいごと」ばかりでは説明がつかない。「いびつな真珠(バロックの語源)」の持つ深い意味を考えた。2015/03/24
みそさざえ
7
このところいつも聞いているのは結局はバロック音楽なので、改めてもう少し読んでみようかと。半分ぐらいは知らなかったり忘れていた内容。2019/05/17
misui
3
劇場的な音楽空間/オペラやオラトリオの誕生、楽器の発達などを通してそれまでにはなかった感情表現が可能になり、イタリアを中心に各国の状況(宗教改革、ブルボン王朝、三十年戦争…)によってそれぞれ隆盛する。整理がついてわかりやすい。2023/12/02
adelita
0
バロック音楽と言ってはみるもののよくわかっていないのでお勉強に。時代背景などもよくわかって、ざっくり概観できたように思います。読みやすかったし面白かった。でも音楽そのものももっと聴かなきゃいけないし、西洋音楽史ももっと知らないといけないなぁと思ったのでした。余談ですが、『オペラ・ブッファの進撃』という節タイトルに、漫画を思い出してにやっとしたのでした。Sic transit gloria mundi。2014/01/03