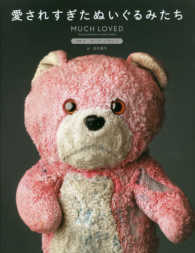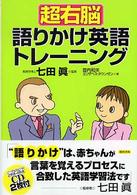出版社内容情報
言語がどのように出現して進化したか? 他者の心(意図)を読む能力こそが言語コミュニケーションに重要であることを提起し,それを裏付ける理論およびデータとともに説得力をもって解説する.言語学,認知科学,進化生物学などを統合した瞠目すべき見解を示した一冊
内容説明
他者の心を読む能力を基盤とするコミュニケーションこそが、言語の起源・進化の謎を解く鍵である―。言語学、認知科学、進化生物学などの成果を把握したうえで、それらを統合した瞠目すべき見解を説得力をもって提示する。「人間とは何か」という根源的な問いに興味をもつすべての人へ。
目次
第1章 コミュニケーションへの二つのアプローチ
第2章 コミュニケーションシステムの出現
第3章 認知とコミュニケーション
第4章 意図明示コミュニケーションの起源
第5章 個々の言語を組み立てる
第6章 進化的適応
エピローグ 大問題に答える
著者等紹介
スコット=フィリップス,トム[スコットフィリップス,トム] [Scott‐Phillips,Thom]
中央ヨーロッパ大学上席研究員。認知と文化の関係が主な専門領域で、特にヒトのコミュニケーションに特有の性質に関心がある。2011年に欧州人間行動進化協会の新進研究者賞、2010年に英国心理学会の卓越博士研究賞などを受賞
畔上耕介[アゼガミコウスケ]
1973年生れ。翻訳家、放送大学選科履修生、東京言語研究所理論言語学講座受講生。言語学と数学の哲学的基礎に関心を持つ他、自閉症スペクトラム(ASD)者としての体験から着想した人間精神の構造についての仮説を研究している
石塚政行[イシズカマサユキ]
1987年生れ。東京大学大学院人文社会系研究科助教。専門はバスク語・認知言語学
田中太一[タナカタイチ]
1988年生れ。東京大学大学院人文社会系博士課程。専門は認知言語学・日本語学
中澤恒子[ナカザワツネコ]
1956年生れ。東京大学大学院総合文化研究科教授。専門は理論言語学
西村義樹[ニシムラヨシキ]
1960年生れ。東京大学大学院人文社会系研究科教授。専門は認知言語学
山泉実[ヤマイズミミノル]
1979年生れ。大阪大学大学院言語文化研究科准教授。専門は意味論・語用論、特に「なぜヒトだけが言葉を話せるのか―コミュニケーションから探る言語の起源と進化」を源流の一つとする指示参照ファイル理論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
zoe
mim42
ニッポニテスは中州へ泳ぐ
iwtn_
清水勇
-
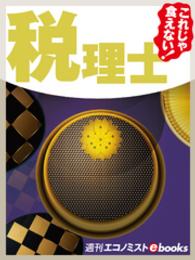
- 電子書籍
- これじゃ食えない!税理士