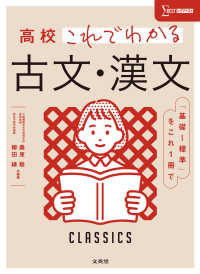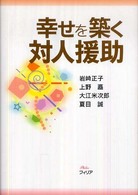出版社内容情報
「小1のカベ」とは,子どもが「学校的コミュニケーション」に身を置くようになるまでのハードルでもある.教師と子どもの言葉と身振りがつくる教育の空間の具体像を追う著者の試みが,教える研究(教育実践研究)から,教室を生き,学ぶ側を中心にした「学習実践研究」へと心理学を更新してゆく.
内容説明
「共謀」される授業と「学校のことば」の向こうへ。学ぶ子ども、悩む先生と共にある、“協働的エスノグラフィー”のこころみ。教育に研究がかかわるとはどういうことか、著者渾身の回答。
目次
序章 学校の心理学から実践のための研究へ
第1章 児童になる・生徒になるということ―小学校に入学する
第2章 授業を生きる
第3章 教室において「書くこと」を学ぶということ
第4章 学びの場としての教室空間
第5章 指導者のジレンマと成長
第6章 多様性に戸惑う教室
終章 学びの場にかかわるということ
著者等紹介
石黒広昭[イシグロヒロアキ]
立教大学文学部教授(教育学科、同大学院文学研究科教育学専攻)、発達心理学・教育心理学。宮城教育大学教育学部助教授、北海道大学教育学部助教授などをへて2006年より現職。博士(教育学)(慶應義塾大学)。日本発達心理学会、日本心理学会、日本教育心理学会、日本認知科学会、American Educational Research Association(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Arick
0
教員の目とはまた別の目、メタな視点で授業や教室を見て書かれている。教員の自分からは見えない(見ていない)景色があった。第5章指導者のジレンマと成長が特に印象深い。「子どもたちは学校において「リベラルな社会」を築く主体として育つのは難しいかもしれない。民主的な運営、他者に対する配慮のありかたを子どもたちが学ぶ場として教室を位置づけようとするならば、指導そのものの意味とありかたが変わらなくてはならないのではないか」(p.135) どう変えていくか。実践者としての矜持を見せたい。2017/02/20