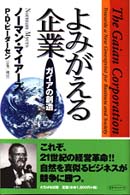出版社内容情報
子どもによる殺傷事件・いじめ、不登校、親による虐待、教師のストレスなど、深刻な教育の現実を打開する道を探る。スクールカウンセリングや専門家による地域ネットワークを提唱。
内容説明
優しく深く癒される著者の世界へ。その世界から、生徒や教師、教育を捉えることを訴える。
目次
教育臨床心理学への道
1 教育現場の現実(子どもの攻撃性とその対応;いじめ・いじめられ、暴力問題;見え隠れする子どもの虐待―教育臨床から;教師の苦しみ、癒しを求める声)
2 思春期・青年期へのアプローチ(自己の解体と再編成―プロセスの保障について;「悪」的なるもの、秘密の共有;聴きとられること、語るということ)
3 スクールカウンセリング考(スクールカウンセリングを考える;スクールカウンセリングの実際(生徒と教師の人間関係を中心に;必要を軸とした輪を))
著者等紹介
横湯園子[ヨコユソノコ]
1939年静岡県に生まれる。1963年日本事業大学社会福祉学部卒業。国立国府台病院児童精神科病棟内学級教師、市川市教育センター指導主事、女子美術大学助教授、北海道大学教授を経て、現在、中央大学文学部教授、臨床心理士
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
10
2002年初版。子どもを取り巻く環境は厳しさをましています。この本は登校拒否の子どもたちについて、教育臨床心理学の立場から論じられた本です。不登校状態に陥った原因はいじめや虐待などいろいろとあります。しかし、学校へ行けていない自分を子どもたちが引き受けざるをえず、程度の差はあれ学校、自分、親、友達、存在する意味など「何か?」の根源的な問いにぶつかります。それは、子どもにとって大きな苦悩だと思います。そうした子どもたちに対してカウンセラーや専門職はどのように向き合う必要があるのか、考えることができました。2014/09/04
山がち
0
日本の教育が高度に競争的でストレスフルであるという国連の子ども権利委員会の所見は、もっと共有されて欲しいと思ったが、これは教育に限らず様々な場面で起きていることであるということも自覚が必要であろうか。また、悠という生徒の事例が非常に興味深かった。母親に対してスクールカウンセリングの依存を批判したり、教師に対して自己主張を高度に行うように変わっていったり、自身がいじめを行う側へと変わったり、周囲の対応も含めて驚くことが多かった。しかし、それでも一人の人間として様々な理解がなされているというのは忘れられない。2013/12/15
-
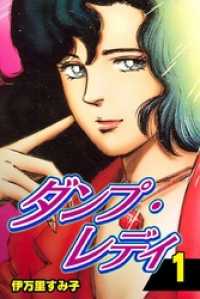
- 電子書籍
- ダンプ・レディ(1)