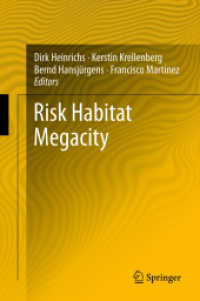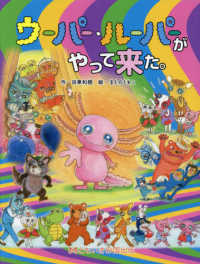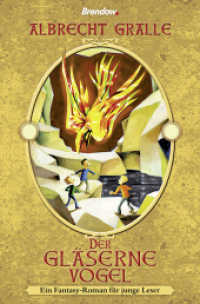出版社内容情報
全国のコミュニティに、コンビニはなくとも、学校はなくとも、公民館・公民館的なるものはある。地域の住民が、移住者が、「だれか」が、「ほしい未来を自分でつくる」場として、まちそのものを公民館のようにして再発明する実践のヒントを詳細に、しかも親しみやすい語り口で問いかける。歴史をふりかえり、海外にも飛びながら考える公民館の未来。
内容説明
「ほしい未来を自分たちでつくる」場へ。全国のコミュニティに、コンビニや学校はなくとも、公民館・公民館的なるものはある。地域の住民が、移住者が、「だれか」が、自分たちの未来のコミュニティを自分たちでつくる場を再発明するヒントにあふれた本。歴史をふりかえり、海外にも飛びながら考える公民館の未来。
目次
序 「よきこと」に気づいて、実践する(他者を気遣う、自分を取り戻す;焦点化するコミュニティ;公民館をもう一度発明する)
第1章 社会の最先端を体験できる住民自治の場(ありたい生活を実装する住民自治の場―ナトコ映画『公民館』に見る公民館;新しい自治の担い手の育成―公民館構想の想い;構想と現実と―公民館構想の継承と変容と;公民館が欲しくてたまらなかった―住民の想い)
第2章 ひとが育つまち(日本社会の縮図―「ひとが育つまち」の原点;まちは「ひと」―語りあう子どもとおとなたち ほか)
第3章 「農的な生活」の自治論(生きるを分けあう―「共居」のまちづくり;博打をとるか、麻薬をとるか―プロジェクトの背景 ほか)
第4章 公民館の懐かしい未来(苦悩する若者たち―エジプトの社会と人々の生活;けん玉は人生だ―日本への関心;社会の縮図で希望―エジプト式公民館に見る懐かしい未来)
結 「よきこと」に気づいて実践するアート
著者等紹介
牧野篤[マキノアツシ]
1960年生まれ。東京大学大学院教育学研究科教授。名古屋大学大学院教育学研究科博士課程修了。博士(教育学)。中国中央教育科学研究所客員研究員、名古屋大学大学院教育発達科学研究科助教授、教授を経て、2008年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
takao
Guro326