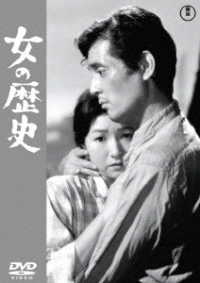出版社内容情報
学校とは何であり、そして何でありうるのか? 「学びの共同体論」「公共圏論」などについて、重要な論考を一書にまとめる。
学校とは何であり,そして何でありうるのか? 近代以降の教育を根源的に批判しながら,現実の学校に足を運び人と出会いつづけ,そこに可能性を見出してきた稀有な研究者である著者が,「学びの共同体論」「公共圏論」「リテラシー論」そして「人」について,近年もっとも重要な論考を一書にまとめる.
第I部 学校の哲学
1 交響する学びの公共圏――身体の記憶から近代の脱構築へ
2 学校という装置――「学級王国」の成立と崩壊
3 リテラシーの概念とその再定義
4 公共圏の政治学――両大戦間のデューイ
5 学びの共同体としての学校――学校再生への哲学
第II部 哲学的断章
1 越境する知の断章
2 コミュニケーションとしての演劇と教育――如月小春との対話
3 祈りの心理学・希望の保育学――津守真に学ぶ
4 授業研究の軌跡から学ぶもの――稲垣忠彦の「教育学(ペタゴジー)」
5 死者の祀りとしての「私」――宮澤賢治の言葉と身体
【著者紹介】
佐藤 学:東京大学大学院教育学研究科教授
内容説明
学校を問い改革し続ける著者の渾身のアンソロジー。実験的で挑戦的な創意によって執筆した論文集。
目次
1 学校の哲学(交響する学びの公共圏―身体の記憶から近代の脱構築へ;学校という装置―「学級王国」の成立と崩壊;リテラシーの概念とその再定義;公共圏の政治学―両大戦間のデューイ;学びの共同体としての学校―学校再生への哲学)
2 哲学的断章(越境する知の断章;コミュニケーションとしての演劇と教育―如月小春との対話;祈りの心理学・希望の保育学―津守真に学ぶ;授業研究の軌跡から学ぶもの―稲垣忠彦の「教育学(ペダゴジー)」
死者の祀りとしての「私」―宮澤賢治の言葉と身体)
著者等紹介
佐藤学[サトウマナブ]
1951年生まれ。東京大学大学院教育学研究科教授。教育学博士(東京大学)。三重大学教育学部助教授、東京大学教育学部助教授を経て、1997年より現職。東京大学大学院教育学研究科長(2004年‐06年)。エル・コレヒオ・デ・メヒコ招聘教授(2001年)、ハーバード大学客員教授(2002年)、ニューヨーク大学客員教授(2002年)、ベルリン自由大学招聘教授(2006年)。全米教育アカデミー(NEA)会員。日本学術会議第一部(人文社会科学)部長。日本教育学会前会長。アメリカ教育学会(AERA)名誉会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 【単話版】スライムは最強たる可能性を秘…
-

- 電子書籍
- 体力の正体は筋肉 集英社新書