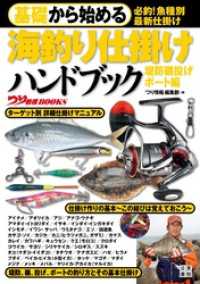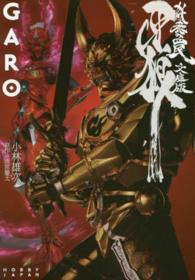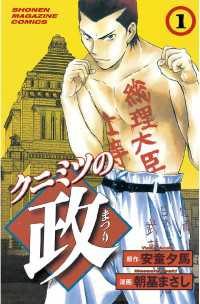出版社内容情報
東京23区(500mメッシュの2337地区)および南関東(333市区町村)のバブル期をはさむ社会変動を,詳細な社会地図に表現.口絵カラー図7点,本文内地図285点と,懇切な解説によって1975年から1990年にいたる東京圏の変化を明瞭に把握する.
内容説明
本書は、世界都市化、バブル崩壊と東京が激動した、直前の1975年と直後の1990年の2つの時点で、東京圏の空間構造を社会地図の手法で視覚化し、この間の変動の内実を明らかにしたものである。社会地図の手法とは、南関東の1都3県プラス茨城県南部を333市区町村に、東京23区を縦横500メートル・メッシュの2337小地区単位に分け、この単位地区毎に社会的特性を濃淡の地図に表現するものである。さらにクラスター分析を用い、類似した地域特性を持つ単位地区をまとめ、その総括的な構造と変動を示した。
目次
1 総括編(社会地図:範囲と方法;東京圏の空間構造とその変動 1975‐90)
2 領域編(東京圏の人口動態;家族から見た東京圏;住宅から見た東京圏;東京圏の産業動態;職業階層から見た東京圏)
3 テーマ編(貧困の空間分布;外国人居住者の空間分布;教育行動の空間分布;生活文化の空間分布;投票行動の空間分布;生活圏の編成)
4 データ編(データおよび地図の構成;社会地図研究の方法)
著者等紹介
倉沢進[クラサワススム]
放送大学教養学部教授、東京都立大学名誉教授
浅川達人[アサカワタツト]
放送大学教養学部助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。