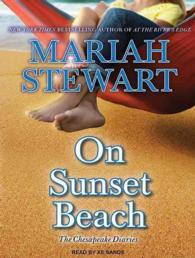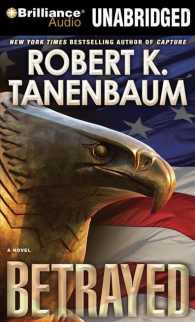出版社内容情報
東アジア経済のなかで、日本が果たすべき役割とは何か。経済発展の道筋をたどる「組立型工業化論」から東アジア経済の行方を探る。
内容説明
中国経済の躍進が伝えられている。韓国経済も1997年末の経済危機を克服して着実な成長を取り戻しつつある。日本経済もバブル崩壊後10年以上をかけてようやく復調しつつある。この間、東アジア3ヵ国間の経済関係は極めて活発化してきた。2004年には韓国の最大の輸出相手先は中国となり、日本でも2005年においては長年輸出先第1位であった米国を抜いて中国が第1位となった。政治関係の冷却を横目に経済関係においてはこの3国間の結びつきは堅固なものとなりつつある。本書はこのような3国間の経済関係、ことに貿易関係が急速に進展したという事実を各国の「工業化の発展パターン」との関連で読み解こうとするものである。
目次
問題意識と本書の課題
1 組立型工業化仮説とそれを可能にした条件(組立型工業化仮説;NC工作機械の発達;韓国企業の中国進出と組立型工業化の進展)
2 東アジア貿易関係の特質(東アジア諸国との貿易関係;工業化のパターンから見た日本の韓中台貿易;幸せな共存かあるいは脅威か)
アジアの中の日本とその課題
著者等紹介
服部民夫[ハットリタミオ]
1947年大阪府生まれ。1971年同志社大学文学部社会学科卒業。特殊法人アジア経済研究所(現日本貿易振興機構アジア経済研究所)研究員。同研究所在職中、ソウル大学校、ハーバード大学にて客員研究員。1991年東京経済大学経営学部教授。1996年同志社大学文学部社会学科教授。東京大学大学院人文社会系研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 萬葉集研究 〈第26集〉