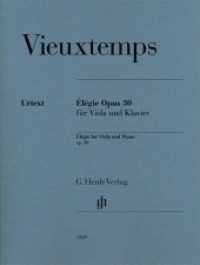出版社内容情報
百貨店や婦人雑誌の通販や月賦販売という、二つの小売革新が生み出した新しい消費社会の形成と変容を、豊富なデータから描く。
二つの小売革新による新しい消費のパラダイムの登場を戦前期日本社会に見いだす.消費者の価値観が転換し流通構造も変貌していく動態を,百貨店の通信販売・漆器・お茶・婦人雑誌代理部など具体的な対象を詳細に分析し,普遍性と個性の両面から描きだす日本型大衆消費社会の形成プロセス.
序章 問題の所在
第I部 戦前期日本の通信販売
第一章 数量的概観と担い手の性格
第二章 代金引換郵便の意義と「限界」
第三章 百貨店による通信販売の日本的展開
第四章 通信販売による宇治茶ブランドの全国展開
第五章 婦人雑誌代理部の歴史的役割
補論 同業者組織による通信販売の規制――自転車の場合
第II部 戦前期日本の月賦販売
第六章 数量的概観と担い手の性格
第七章 基盤整備の遅れと経営的対応
第八章 伊予商人による漆器販売の地域的展開
第九章 月賦百貨店の成立と大衆市場
終章 総括と展望
【著者紹介】
満薗 勇
満薗 勇:日本学術振興会特別研究員
目次
第1部 戦前期日本の通信販売(数量的概観と担い手の性格;代金引換郵便の意義と「限界」;百貨店による通信販売の日本的展開;通信販売による宇治茶ブランドの全国展開;婦人雑誌代理部の歴史的役割;同業者組織による通信販売の規則―自転車の場合)
第2部 戦前期日本の月賦販売(数量的概観と担い手の性格;基盤整備の遅れと経営的対応;伊予商人による漆器販売の地域的展開;月賦百貨店の成立と大衆市場)
著者等紹介
満薗勇[ミツゾノイサム]
1980年千葉県生まれ。2004年東京大学文学部卒業。2010年東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了、日本学術振興会特別研究員(PD)。現在、立教大学経済学部兼任講師、神奈川大学経済学部非常勤講師、高崎経済大学経済学部非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。