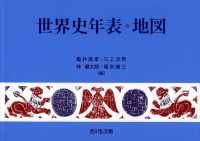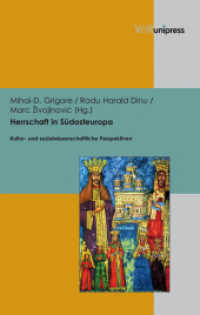出版社内容情報
宗教・宗派間の対立は民族問題と結びつき,今日にいたるまで争いを生み出している.普遍宗教としてのキリスト教により統合されつつも闘争と融和が錯綜するヨーロッパの中世から現代を舞台に,「他者」を容認するということの意味,寛容とは何かを解明する.
目次
近世フランス史における宗教的寛容と不寛容―ナント王令四〇〇周年をめぐる研究動向から
第1部 中世の遺産(不寛容なる王、寛容なる皇帝―オットー朝伝道空間における宗教的寛容;中世シチリアの権力構造―異文化集団の共存と対立;レコンキスタ終結後のグラナダ王国における不寛容―その起源と生成)
第2部 近代への曲折(イングランド国教会はカトリックである―一七・一八世紀のプロテスタント・インタナショナルと寛容問題;アイルランドにおける宗派間の融和と対立―一八二〇年代のダブリンの事例から;一八世紀フランスのフリーメイソンと寛容思想;近代フランスにおける公認宗教体制と宗教的多元性;現代フランス・プロテスタントと「寛容」言説―ナント王令四〇〇周年を中心に)
著者等紹介
深沢克己[フカサワカツミ]
1949年生。東京大学大学院人文社会系研究科教授
高山博[タカヤマヒロシ]
1956年生。東京大学大学院人文社会系研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
M
4
近代以降、宗教の信仰の力は失っていったが、それ以前の社会では何故、宗教の影響力が強く、信仰と他者は共存し得なかったのか、あるいは相互に寛容は育まれなかったのかを冷静に俯瞰できる現代社会だからこそ、改めて考える意義があるのではないかと感じる。教義に反した血みどろな戦争をしてまで、キリスト教は何故、繁栄を望んだのか、それぞれの文明の中で養われた宗教の生理ともいうべきものと時代の中で寛容と不寛容の歴史を紐解き、社会を見つめ直すと何が見えてくるのか。日本ではキリスト教が根付かなかったことなども改めて考えてみたい。2020/11/01
陽香
2
200610202015/04/14