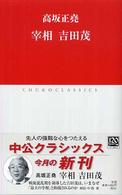出版社内容情報
日本の伝統的な芸術や芸能、武道の分野のなかで重要な役割を担い、日本の文化全般にとって美学的で哲学的な原理として長く論じられてきた間(ま、あいだ、あわい)や間合いについて生態学的現象学の視点からそのダイナミズムを明らかにする。
内容説明
「間合いの本質とは、このリズムにこそある」生態学的現象学の視点から明らかになる間(ま、あいだ、あわい)や間合いのダイナミズム。
目次
第1章 生態学的現象学とは何か
第2章 技と型、その音楽的本質
第3章 間合いとリズム
第4章 花と離見の見
第5章 流体としての身体
第6章 間合いとアフォーダンス
著者等紹介
河野哲也[コウノテツヤ]
立教大学文学部教育学科教授。博士(哲学)。専門は哲学、倫理学、教育哲学、NPO法人「こども哲学・おとな哲学アーダコーダ」副代表理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。