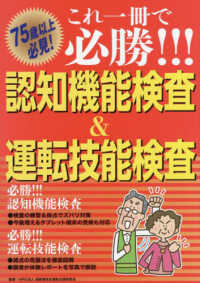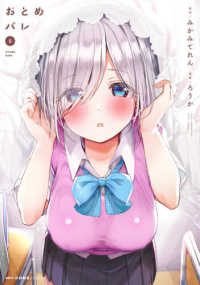内容説明
日中、日韓の文化のあいだで、学校、大学のなかで、あるいは法廷や介護の現場で、「ズレ」をこそ生きる私たちの心理学を試みる。
目次
ズレとしてのコミュニケーション
第1部 対立から共同性へ―生成の現場としてのディスコミュニケーション(ズレの展開としての文化間対話;異文化理解における対の構造のなかでの多声性―お小遣いインタビューでみられる揺れと安定を通して;ズレを通じてお互いを知りあう実践―学校臨床のディスコミュニケーション分析)
第2部 日常性の中のディスコミュニケーション(ケア場面における高齢者のコミュニケーションとマテリアル;未来という不在をめぐるディスコミュニケーション―大学生の揺れ続ける未来と共にある実践の在り方;回想とディスコミュニケーション)
第3部 ディスコミュニケーションを語り合う(見える文化と見えない文化―「規範化」から見た考察;座談会 ズレながら共にあること)
第4部 ディスコミュニケーションを語る視座―理論的検討(ディスコミュニケーション分析の意味―拡張された媒介構造(EMS)の視点から
ディスコミュニケーション事態の形式論―言語的相互作用の微視分析に向けて)
著者等紹介
山本登志哉[ヤマモトトシヤ]
早稲田大学人間科学学術院教授
高木光太郎[タカギコウタロウ]
青山学院大学社会情報学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
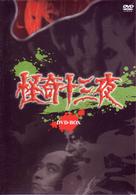
- DVD
- 怪奇十三夜 DVD-BOX
-

- 和書
- 一豊の妻 文春文庫