出版社内容情報
信頼と裏切りの起源とメカニズムを,進化ゲーム論と実験データからみごとに解明し,日本が従来の集団主義社会を脱し,他者一般に対する信頼で成り立つ開かれた社会を形成することの大切さを説く. 日経・経済図書文化賞受賞
内容説明
「安心」を求める集団主義は信頼を破壊する。世の中で最も信頼できるはずの金融機関は、なぜあれほどまでに国民の信頼を裏切り、逆に総会屋を「信頼」したのか。進化ゲーム論からのみごとな推論と実験データから大胆に提言する現代人の必読書。
目次
1章 信頼のパラドックス
2章 信頼概念の整理
3章 信頼の「解き放ち」理論
4章 安心の日本、信頼のアメリカ
5章 信頼とコミットメント関係の形成
6章 社会的知性としての信頼
終章 開かれた社会の基盤を求めて
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
キク
55
「正直は最大の戦略である」信頼と裏切りの起源とメカニズムを進化ゲーム論と実験データから、こう結論を導き出している。相手を信頼して正直に行動して、もし裏切られたら一度だけ仕返しをして、また信頼する。その行動原理は「相手をいつも疑う」「相手をいつも騙そうとする」よりも最終的には自分の益となっていた。なんか、とても素敵な結論だ。2024/04/22
きいち
40
先日亡くなられた山岸氏の主著。社会的不確実性(騙される可能性アリ)と機会コスト(他から買った方が得アリ)が大きくなると(ってすなわち今ですね)、ガチガチに安心を保証する世の中よりも、デフォルトでとりあえず信頼しておいて順次判断していく世の中の方が、社会的な利益は大きくなる…おお!直近読んだジェイコブズ「市場の倫理」ではないか!バシバシつながってきてゾクゾクしながら読了。特に、信頼(する側の問題)と信頼性(される側の問題)を明確に分け、「信頼する」という姿勢こそがより社会の潤滑油機能を果たすという論に響く。2018/08/25
キク
17
昔、糸井重里がこの本の様々な考察や実験を通して得られた「正直ということは、最良の戦略である」という結論について「それは『ほぼ日』の精神的父親となった」と熱く語っていた。確かに、関わるなら「正直ではない優秀な人」より「正直だけどドジな人」の方を、僕も選ぶ気がする。そんな、選べる立場でもないけど。信頼、信用、安心ということがどう違って、どういうことなのか教えてくれる良書でした。2020/12/16
たんたん麺
16
人々の間に信頼が存在しなければ社会が成り立ち得ないことは、誰でも理解できるだろう。信頼は人々の間の、あるいは組織の間の関係を可能とする社会関係の潤滑油であり、信頼なくしては、社会関係や経済関係を含むすべての人間関係の効率はいちじるしく阻害されることになる。本書は、一つの中心的なメッセージをめぐって書かれている。集団主義社会は安心を生み出すが信頼を破壊する。というメッセージである。仲間うちで安心していられる関係(例えば山奥の共同体)に埋没していると人間一般に対する信頼が育ちにくくなることを主張するものである2014/05/05
ねお
15
従来の信頼の定義を見直し、信頼性の中で安心と信頼を分離した上で、進化ゲームを用いて「集団主義社会は安心を生み出す一方信頼を破壊する」ことを論じ、同時に、社会心理学者の関心から薄れている「心が社会的環境に与える影響」について分析する。筆者によれば、信頼には2つの機能がある。従来の信頼研究では、信頼の関係強化機能が盛んに論じられてきたが、本書の独自性は信頼の関係拡張機能を明らかにした点である。信頼は、閉ざされた関係(ヤクザ型コミットメント関係)から離脱し、自発的に新たな関係を形成させるものでもあると主張する。2022/05/31
-
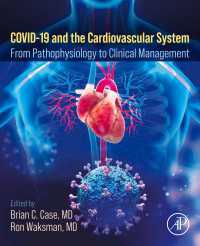
- 洋書電子書籍
- COVID-19 and the Ca…
-
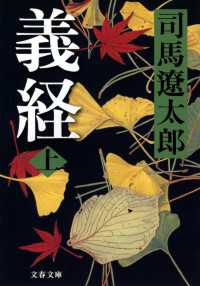
- 電子書籍
- 義経 〈上〉 文春文庫




