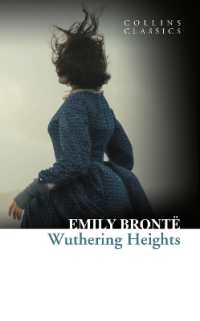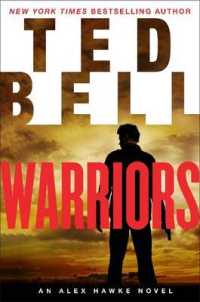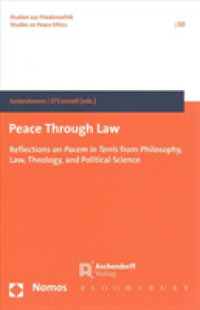出版社内容情報
昨今の教育改革論議が見誤っている教育・経済・社会の関係を,長年の実証研究をふまえて検討しなおし,未来に向けた投資である学校教育の有効性を明らかにしてゆく.学校・会社・家庭の相互依存関係から,生活と人生の未来像をデザインし,21世紀の「教育社会」を構想する.
内容説明
教育の未来に向けて社会工学からの提案。問題が多発する現在、あらためて学校・会社・家庭の相互関係を実証的に解明し、学校教育の有効性を再確認する。教育が社会生活の中心をなす「教育社会」へのたしかなデザイン。
目次
序章 教育改革―五つの誤り
1章 学歴社会の経済構造
2章 理念なき「大学の大衆化」
3章 「教育と経済」の不幸な関係
4章 「知識」と「対話」―教育市場との関係
5章 「移動」と「知識」―グローバリゼーションの衝撃
6章 学校・会社・職業―学歴社会の未来像
7章 学校・家族・生活―ゆとりの生活設計
8章 人生設計と学習社会像
著者等紹介
矢野真和[ヤノマサカズ]
1944年東京都生まれ、三重県育ち。1968年東京工業大学工学部卒業。民間会社勤務を経て、東京工業大学工学部助手。1974年国立教育研究所研究員。1981年広島大学大学教育研究センター助教授。現在東京工業大学大学院社会工学専攻教授。東京大学大学総合教育研究センター教授(併任)工学博士
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
29
高等教育、また生涯学習を考えるうえでの基本的な枠組みを提供してくれる一冊。◇経済の立場のみにいる人は高等教育(および社会人の学び直し)を家庭・もしくは自己による投資としてしかみないし(だから無償化にも反対)、教育の世界にいる人は金で教育の効果を測ることそのものに反発する。両者のロジックは重ならない。だから、この本のような、教育の共同財としての社会的な価値をエビデンスで語ることは、その両者の間に橋を架ける貴重な取り組み。世の中変えたいなら相手の土俵に踏み込まねば、だ。◇「明るく中退、元気に復学」!いいわあ。2017/07/09
りなこ
1
「高校をコミュニティカレッジに」「明るく中退、元気に復学(略)入試政策だけで、制度(高校)と制度(大学)の接続を制御しようとする発想に無理がある。(略)知識が役に立つことを実感するためには、働いてみる経験が必要(略)必要がないと思えば、学ぶ必要はない」「会社探しのビジネス化ではなく、大学は人生を探索する場所にならなければならない(略)失敗を許すのが大学の特権である」etc。平日のゆとりと高齢者の生活設計、家庭と仕事の弾力的なバランスの三点を改革のポイントとして、変動する社会の不公平とか歪みを是正しようとい2013/06/29
Kei
1
「今日の学校教育に求められているのは、これからの知識社会を支える普通の人のスキルアップである」「税金が何のために投入されているのか、誰のための教育か、という問いに教師は答えられなければならない」「見知らぬ他人の存在と協力を理解するのが道徳である」「学校教育にできることは、『知識』の理解にむけて、たゆみのない『対話』を続けること」「人々の人生設計も見直す時期にきており、重要なのは未来の人生を秩序立てる焦点は何かということ」 約10年前の本になりますが、現在でも十分当てはまります。考えさせられます。2012/11/11
-
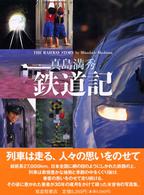
- 和書
- 鉄道記