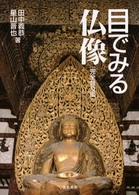内容説明
本書は、化学を中心とした新しい「手法」と、その応用で得られた考古学の重要な「成果」のいくつかを併せて平易に解説したものである。考古学と化学の結びつきという視点では、前二書の延長線上にあるといってもよいが、本書は決してその続編というわけではなく、内容も執筆陣もまったく新しい構想のもとに企画された独立の読物である。
目次
歴史科学と自然科学のあいだ
化学と考古学の接点
考古学における14C年代測定―高精度化と信頼性に関する諸問題
日本列島に原人は存在したか(ルミネッセンス年代測定法による検証;古地磁気からさぐる)
日本列島の旧石器時代人骨はどこまでさかのぼるか―化石骨の年代判定法
中国古代文明をさぐる―鉛同位体比による研究を中心に
先史人は何を食べていたか―炭素・窒素同位体比法でさぐる
日本のイネはどこからきたか―DNA解析
皇朝十二銭の原料をさぐる―元素分析と鉛同位体比分析
文化財保存とオゾン層破壊―臭化メチル殺虫燻蒸に代わる方法は?
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
の
1
考古学を取り巻く科学の状況は常に変化、発達している。年代を炭素14法で測るといった直接的な関係は勿論のこと、環境破壊による遺物の汚染といった間接的な関係も、そこには存在する。また、弥生時代の起源時期のように、一つの科学の進歩で、何十年も掛けて其処まで築き上げてきた知識が根底から覆されるなど、科学の優位性が相当高く置かれていることに驚いた。理数系の専門的な用語も多かったが、肝心な所はグラフや表に纏めていたりと、かなり分かりやすく出来ている本。2011/05/06
Book shelf
0
考古化学系の本のシリーズ3作目。今や、考古学には自然科学的な研究方法が欠かせなくなっています。いよいよ考古学者も科学を学ばないといけない時代になってきました。