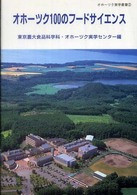出版社内容情報
日本人は何を,どんな道具で,どう調理して,食べてきたのか.食物はどのようにして手に入れたのか.それは,体の仕組みや健康とどう関わっていたのか.縄紋時代から8世紀頃までの「食」の実態を考古学的立場から迫り,現代の食文化との関連を探る.
内容説明
食物はどのようにして手に入れ、どんな道具で、どう調理していたのか。それは、体の仕組みや健康とどう関わっていたのか。縄紋時代から8世紀頃までの「食」の実態を考古学的立場から迫り、現代の食文化との関連を探る。
目次
序章 日本の食
第1章 豚・鶏・茸・野菜
第2章 米と塩
第3章 煮るか蒸すか
第4章 肉食と生食
第5章 箸と茶碗
第6章 食とからだ
第7章 犬・氷・ごみ
第8章 最後の始末
終章 米と日本人
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
翠埜もぐら
16
家畜、米、米の食べ方と塩、調理器具に食器、食料としての犬など、そして最終的なお話として排泄までを、考古学的な遺物から考察。最近日本に最初に入ってきた米がジャポニカではなかったとか、炊いたのか、煮たのか、蒸したのかとか、箸の広まり方とか、どんどん昔と話が変わってきていて楽しい楽しい。でも「食べてしまう物」は基本的に残らない。木簡や残滓から判断しなくてはならない訳だけれど、同位体などを使ったアプローチもあって、考古学が様変わりしてきていることも触れていて面白かったです。まあ20年も前の本なんだけどね。2023/07/31
おらひらお
3
1995年初版。著名な考古学者佐原真さんによる食をテーマにした一冊です。現代では一人でこのような本を書くことはできないような気もします。2017/09/06
まのん
0
食用じゃなくて、単に目覚まし時計として鶏を飼っていたことに違和感2014/01/22
-
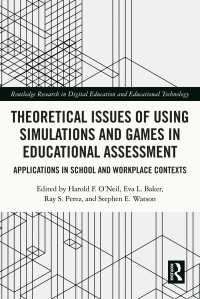
- 洋書電子書籍
- Theoretical Issues …