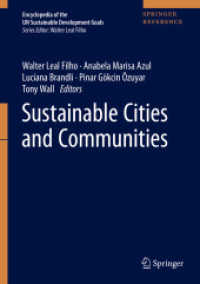出版社内容情報
ぼくは自分の生まれたところを、これまで知らないでいた――。自身のルーツである教会を探すも、なぜか中々たどり着けない。それでもコミさんは気にしない。うまくいかなかったときのほうが、しゃべったり書いたりして楽しいのだ。
温泉地で目の前に来た列車に飛び乗り、海外でもバスでふらふら。気ままな旅はつづく。
初文庫化。
〈解説〉末井 昭
内容説明
ぼくは自分の生まれたところを、これまで知らないでいた―。自身のルーツである教会を探すも、なぜか中々たどり着けない。それでもコミさんは気にしない。うまくいかなかったときのほうが、しゃべったり書いたりして楽しいのだ。温泉地で目の前に来た列車に飛び乗り、海外でもバスでふらふら。気ままな旅のエッセイ。初文庫化。
目次
さてきょうは(親子電球;消えた教会;あかるい冬の日 ほか)
酔ってふらふら(オホーツク;登別温泉;雪が降って ほか)
たびタビの旅(バスにのってふらふらと;サンディエゴの海;ぼくのロング・バケーション ほか)
著者等紹介
田中小実昌[タナカコミマサ]
1925年、東京生まれ。小説家・翻訳家。東京大学文学部哲学科中退。79年、「浪曲師朝日丸の話」「ミミのこと」で直木賞を、『ポロポロ』で谷崎潤一郎賞を受賞。2000年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
107
「さてきょうは」はコミさんの身近なことについて「酔ってふらふら」は日本の中のひとり旅「たびタビのたび」は海外旅行の時のことが書かれている。個人的には日本の旅が好きだ。温泉地や瀬戸内、競輪場などお酒とバス、女の人が好きなコミさんがゆるい文体で書かれている。昭和時代の旅の話なので今と違ってまだまだ時はゆっくり進んで旅という行為には優しい時代だったのだろう。テキヤの子分で全国をまわっていたことも知った。海外旅行はシアトルやカナダ、スペイン、オーストラリアなど。のんびり読める紀行文、お気に入り。図書館本2022/05/01
ホークス
40
1925年生まれで2000年に亡くなった、直木賞作家で翻訳家。若い頃はテキヤの子分など、浮き草のように生きていた。ろくでなし、なのだろう。私は小説は苦手だけど、著者のエッセイは世捨て人の風情があって好きだ。どこか阿佐田哲也とか水木しげるに似ている。穏やかそうな奥に、底なしの虚無感がある。そんな年代でもあるだろう。本書のメインは旅の話。海外が多く、ぶらぶらとほっつき歩く。無頼な著者でも雑誌記事だと大人しいのかと感じたが、それは私が未熟なせい。解説はこれまたろくでなしの末井アキラ氏。愛と敬意がさりげない。2022/07/06
Shoji
40
直木賞作家、田中小実昌さんの随筆です。どのような作家さんか分からず、ウィキペディアなどあたってみました。大正時代に生まれ、戦争にも行き、終戦後はストリップ場で芸の下積みなど、冷や飯も食べたようです。そして、海外での生活経験も豊富。さらに、酒に関してはとてもバンカラなお方だったようです。要は、人生の経験値がケタ違いの御仁なんですね。「酔ってふらふら」、「たびタビの旅」という章が面白かったです。2022/03/29
駄目男
21
この人の本は古書店などで見つけ次第買うようにしている。棚にはまだ未読の本が何冊かあるが、単行本は未だに高いので文庫のみにしている。1925年生まれなので私とは親子ほど年が違う。経歴がなかなかユーニクだ。何度も呉れで育ったことが出てくるが、兵隊暮しが済んで東大で哲学を学んで、テキヤ仕事で東京から北陸へ出かけ、旅費が尽きて一文無し、温泉地の客を狙って易者の仕事。直木賞作家で翻訳家。それに印税でかなりの国を旅してる。闘い済んで日が暮れてじゃないが、まったく羨ましいような生活だ。しかしこの人の書くものはなぜか2025/07/31
ジャズクラ本
13
1つのセンテンスに複数の枝葉がぶら下がっているので、どの方向に展開するのか読めない独特の文体に魅せられながら初の田中小実昌読了しました。紀行文みたいなものですが風土や風物詩よりも喰い物の話題が多い。これがまた旨そうに思えるからタマラナイ。。勿論この人のことだから酒の話しも誠にヨロシイ。哲学的でもあり俗でもあるところが得も言われぬ面白さの源泉。1987年頃の出版。そう言えば子供の頃、酒を呑んでるオッサンたちが出来上がってくると「メートルがあがる」などと言っていました。もはや死語ですね。2023/04/24
-
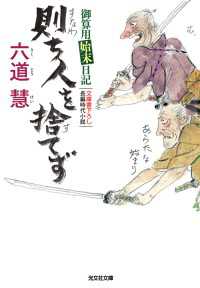
- 電子書籍
- 則ち人を捨てず - 御算用始末日記 光…