出版社内容情報
特技はお料理、按摩、ゴリラの真似――曲者揃いの女たちが、文豪の家で元気にお仕事中!珍騒動と笑いが止まらぬ女中さん列伝。〈解説〉松田青子
内容説明
お料理上手や姉御肌、ハイカラ趣味に特技はゴリラの真似―?文豪の屋敷でのびのび働く女中さんは曲者揃い。初は「いけすかない爺さん」と主人に言い放ち、銀は大恋愛に猪突猛進、百合は昭和の大女優をもたじたじとさせ、千倉家のお台所は毎日てんやわんや。愛情とユーモアに満ちた抱腹絶倒の女中さん列伝。
著者等紹介
谷崎潤一郎[タニザキジュンイチロウ]
明治19年(1886)、東京日本橋に生まれる。旧制府立一中、第一高等学校を経て東京帝国大学国文科に入学するも、のち中退。明治43年、小山内薫らと第二次「新思潮」を創刊、「刺青」「麒麟」などを発表。「三田文学」誌上で永井荷風に激賞され、文壇的地位を確立した。豊麗な官能美と陰翳ある古典美の世界を展開して常に文壇の最高峰を歩みつづけ、昭和40年(1965)7月没。この間、『細雪』により毎日出版文化賞及び朝日文化賞を、『瘋癲老人日記』で毎日芸術大賞を、また昭和24年には、第八回文化勲章を受けた。昭和39年、日本人としてはじめて全米芸術院・米国文学芸術アカデミー名誉会員に選ばれた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
306
これまでタイトルを軍記物の『太平記』からとられたものと思っていたために、家庭を舞台に繰り広げられる様々な騒動(とはいっても明るいもの)をコミカルに描いた物語を想像していた。実際はフィクションのスタイルをとってはいるものの、谷崎家で働いた何人もの女性たちの物語であった。戦前、戦中、戦後と時代が変遷する中で、そんな彼女たち(複数)のあり様も変わっていく。それは同時にその時代を回想する谷崎自身の変容を写し出したものでもあったのだろう。女中からお手伝いさんへと呼び名も変わったが、彼女たちの気質や磊吉(語り手)⇒2025/04/02
mukimi
138
「細雪」が上流階級のお嬢様のお話なら本作はそこに雇われる女中達の物語。昔の日本人女性は(特に女中は)無口で従順な脇役なんだろうと先入観を持っていたが、意外にも皆個性的で自我もしっかりしていて面白い。そして雇い主も彼女たちを実の娘のように可愛がり色々世話を焼いてあげるのが人情の厚い昭和初期の日本を感じさせてもらえて楽しい。谷崎潤一郎はちょっとどろっとした愛憎劇もいいけど「強く元気な女」を生き生きと描いた本作もだいぶいい。これが晩年の作というのも興味深い。谷崎自身無邪気な女達に救われて生きていたのだろう。2025/05/04
ケイ
104
女中についての話。創作的部分もあるだろうが、戦前から昭和三十年代の女中たちの描写なのに、今と変わらないじゃないかという印象。女中同士の同性愛とか、人工授精なんて言葉まで出てくる。最初に来た女中が鹿児島出身だからと鹿児島から次々に若い娘がやってくる様子なども楽しかった。スケベ的な描写は、谷崎だから仕方ない(まあ、このくらいまではね)。京都の地名は馴染みがあり、想像しやすい場所などが多いのだが、南禅寺のそばとか、糺の森あたりとかなんてまあ裕福であることだ。足の裏の白さとか、彼のフェチ的傾向ももらさずわかる。2023/08/09
たま
68
ブックオフで見つけた文庫。昔読んだしドラマを見た記憶もあるが、今はPC的にどうなの?と思いつつめくると、出版社も苦慮したようで2021年の改版の解説は松田青子さん。谷崎を茶化して女中さんたちを生き生き描く挿絵(山口晃)も良い。個性的な彼女たちが容貌をネチネチ描写する谷崎を圧倒する※。単行本は1963年。住み込みの女中さんが長期間勤める時代はその頃、高度経済成長と冷蔵庫や洗濯機の普及とともに終わった。ここに描かれた濃密な人間関係と風俗は(私は子どもの頃を思い出して懐かしいが)過去の貴重な記録となっている。2023/05/28
ヨーイチ
44
作者名より題名が先に記憶されていた。幼少期にテレビドラマを見た記憶がある。その後小説、文芸に親しみ、谷崎を知るようになった。最晩年、文壇の重鎮になった谷崎が自分に仕えてくれた女中達を語った小説のような読み物。一読してとても面白いのは当然として、昔の人たち(戦後ではあるが)の考え方や文化がうかがえてる。こういう世界を撲滅する方向で世の中が進んでいる訳で、その意味でも貴重だと思う。作中では主人公も夫人も彼女たちを大切に遇しているのが分かるが、それとても昔の接し方なのだろう。続く2023/09/19
-
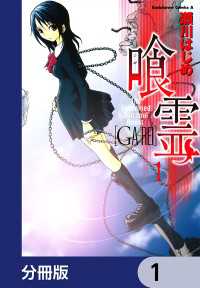
- 電子書籍
- 喰霊【分冊版】 1 角川コミックス・エ…







