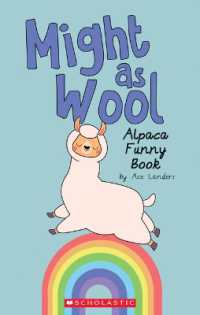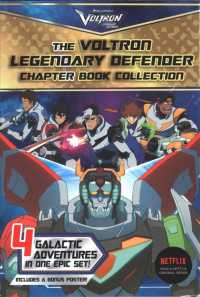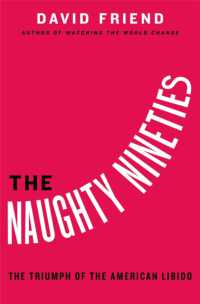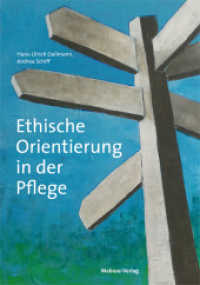出版社内容情報
時には〈日常〉を脱して、魂の目くらむ昂揚を経験することも、人生を豊かにする大切な方法なのだ(本文より)。一九五七年の留学以降、第二の生活拠点となったパリ、創作への啓示を受けたアテネ、作品の舞台となったフィレンツェ、アルジェ……生涯を通じ旅を愛した作家の多幸感あふれるエッセイ集。
〈解説〉松家仁之
目次より
? 地中海幻想の旅から
? フランスの旅から
? 北の旅 南の旅から
辻邦生[ツジクニオ]
著・文・その他
内容説明
一九五七年の留学以降、第二の生活拠点となったパリ、創作への啓示を受けたアテネ、作品の舞台となったフィレンツェ、アルジェ…生涯を通じ旅を愛した作家の多幸感あふれるエッセイ集。
目次
1 地中海幻想の旅から(中部イタリアの旅;フィレンツェ散策;私の古典美術館 ほか)
2 フランスの旅から(ヨーロッパの汽車旅;恋のかたみ;モンマルトル住い ほか)
3 北の旅 南の旅から(ロシアの旅から;森の中の思索から;北の海辺の旅 ほか)
旅について―「あとがき」にかえて
著者等紹介
辻邦生[ツジクニオ]
1925(大正14)年、東京生まれ。東京大学仏文科卒業。63年「廻廊にて」で第四回近代文学賞、68年『安土往還記』で芸術選奨新人賞、72年『背教者ユリアヌス』で第十四回毎日芸術賞、95年『西行花伝』で第三十一回谷崎潤一郎賞受賞。99(平成11)年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まーくん
52
「背教者ユリアヌス」の著者、辻邦生。1957年から4年間、パリに留学。その間に南仏、イタリア、ギリシア、スペインなどを旅する。その後、幾度も欧州各地や北アフリカを訪れる。かつて海外旅行は学者や小説家など限られた人しかできなかったが、彼らの著した小説や紀行で知る彼の地に多くの人々は憧れた。旅は人を<非日常>に置き、精神に糧を与え、人生を豊かにしてくれる。しかし想像力がなければ、旅においても<日常>に埋もれ、魂の昂揚は得られないと説く。確かに歴史を知ってローマを訪れれば見える景色も豊かになるに違いない。2019/01/23
白玉あずき
47
読んだはしから忘れるので、本当に読んだのかどうか・・・ 一番印象に残るのは辻氏の想像力豊かなロマンチストぶり。辻邦生の描くパリと森有正氏のパリをつい比べてしまったのだが、やはり辻氏には私でも没入できる敷居の低さと人間と歴史への高い共感性(小説家の視線)があると思う。私は古い石造りのヨーロッパの町並みには、石独特の人を拒絶するような峻厳さ冷たさを感じずにはいられないが、彼ら両者の表現の違いが興味深い。森氏の自己沈潜と自己分析はちと難解でつらかった。石はその地に生きる人と共に年輪を刻み朽ちていってはくれない。2022/07/26
あきあかね
28
年始に実家に帰った時、柔らかな潮風を感じながら、燦めく明石海峡大橋や月の照らす水面を眺めて走っていると、体の内から生気が湧き上がってくる気がした。日々の生活から離れることで、自身が再生される幸福感は、異国への旅をテーマとしたこのエッセイ集と通じるものがあるだろう。 時に葡萄酒色に時に紺碧に染まる地中海、春の花の香りを湛えたフィレンツェの甘美さ、夢幻の如く揺らめく焔が路地を照らすアッシジの祭礼、様々な人生が露わになるパリの下町の雑踏、冷たい朝霧に包まれた果てしないロシアの白樺の森、⇒2020/01/06
よみこ
16
「身体がこなごなに破裂してしまう」というほどの幸福感を旅に見出していた辻邦生。1970年代船で渡った西欧で、石だたみを歩き、ローマ時代の廃墟を彷徨い、街の変化の速さを体験。そこで感じた生の儚さや死の虚しさこそが、ひたむきに今を生きる人々の知恵をきわ出させているという。のちに飛行機で西欧を訪れるようになって、日常を纏ったまま旅ができるようになったことに言及。非日常で得られる魂の高揚こそが旅の意味であるという。端正な文章に背を押されるように、巷に溢れる継接ぎの旅情報や写真で得られるものは何かを考えさせられた。2020/02/11
地下道入口
5
ある種の詩のようにも読めるし、鋭い文明批評のようにも読める。アルトーの文章に近いところがあるかもしれない。2019/01/22