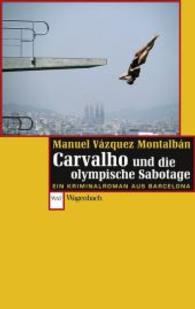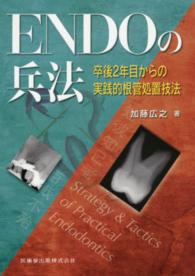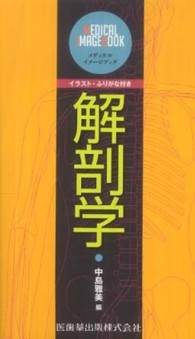内容説明
大正五年、陸軍軍医総監の職を退いた鴎外は、一年半後、帝室博物館総長に任ぜられ、度々奈良に滞在する。在任中の歌で編まれた「奈良五十首」は、『明星』大正一一年一月号に一挙掲載されたもので、茂吉は「思想的抒情詩」と評し、石川淳はそこに鴎外晩年の「物理的精神的な軌跡」を見ようとした。総体としての五十首に込められた本当の含意とは。
目次
1 序にかえて
2 帝室博物館総長兼図書頭としての鴎外
3 「奈良五十首」
4 「奈良五十首」の構成
5 「奈良五十首」の意味
6 「我百首」の構成
7 万葉集と鴎外の「うた日記」
著者等紹介
平山城児[ヒラヤマジョウジ]
1931(昭和6)年、京都生まれ。立教大学名誉教授。立教大学文学部英米文学科卒業。同大学院修士課程修了。さらに、同大日本文学科卒業。同大学院博士課程満期退学。専攻、万葉集及び近代文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Shoji
68
鴎外が帝室博物館の総長をしていた時代、年に一度の正倉院の曝涼(いわゆる「虫干し」のための開扉)にあたり、奈良に出張しては歌を詠んでいました。 それらの歌を解説しています。 奈良の風土や当時の時代背景を織り交ぜながら書かれています。 インテリジェンスの高い内容ですが平易な言葉で書かれています。 国文学が好きな方や、奈良の歴史風土が好きな方は読んで損はないと思います。 2016/12/21
紫羊
18
以前は毎年正倉院展の時期になると奈良に行ったものです。たしか会場である国博の近くに「鷗外の門」という史蹟があったような…読み進みながら興味の尽きることのない、きちんと汗をかいて書き上げられた大変な労作だと思います。2015/12/19
runner M
2
‘夢の国燃ゆべきものの燃えぬ国木の校倉のとはに立つ国’ 正倉院について、こんな歌があったとは… 森鴎外は晩年「奈良五十首」を発表しています。 その概説と評論。 奈良に住む者として例えば東大寺を学ぶときに、正倉院の不思議さに素直に気づくべきだったし、関わってきた人たちについても知る必要があると、痛切に感じました。 妻しげ子を愛し家族を気遣う優しさや、一方で軍医として自説を曲げない頑固さにも触れて、既読の鴎外作品を振り返りたくなる一冊でした。 2015/11/20
bibi
1
鴎外は好きですが、短歌にあまり興味が無くて、彼がどんな歌を詠んでいたのかも知らずにいましたが、この本では一首ごとに丁寧に解説されていて理解が進みました。歌の出来不出来、センスなどは私はわかりませんが、どういう状況でどういう気持ちから詠まれた歌か、彼の憤り、感嘆などが知れて非常に面白かったです。2025/02/10