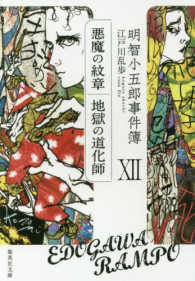内容説明
本居宣長の長男に生まれ、三十代半ばで失明した春庭。文法学者として日本語の動詞活用を研究、『詞の八衢』を著し国語学史上に不滅の業績を残した人物である。学生時代に春庭を知り、その生涯に魅せられた著者が、半生をかけて書き上げた評伝文学の大著。昭和四十九年度芸術選奨文部大臣賞受賞作。
著者等紹介
足立巻一[アダチケンイチ]
1913年、東京に生まれる。神宮皇學館を卒業し、新大阪新聞社(学芸部長など歴任)に勤めるかたわら、児童誌「きりん」を編集。75年、伝記文学『やちまた』で第二十回芸術選奨文部大臣賞を受賞。82年、『虹滅記』で第三十回日本エッセイストクラブ賞を受賞。85年、死去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
傘緑
44
「天地の言霊はことわりをもちて静かに立てり」蜘蛛の巣のように精緻かつ神妙に編み込まれた、呪いにも似た言葉の”やちまた”に、時代を超えて魅入られ、さ迷う者たちの群像劇(この本に引き寄せられた者たちもまた)。「ふしぎですねえ…語学者には春庭のような不幸な人や、世間から偏屈といわれる人が多いようですねえ」この問いかけに私はキニャールの言葉で答えたい気がする。「絶望した人は片隅で生きる。恋におちた人はみな片隅で生きる。書物を読む人はみな片隅で生きる…息もせず、語りもせず、誰の言葉にも耳を傾けず(ローマのテラス)」2017/06/27
Nobuko Hashimoto
26
前々から読もうとしては止まっていた本。本居宣長の長男で、中途失明した国語学者、春庭の評伝。著者、足立氏は学生時代の講義で春庭に魅せられ、40年かけて春庭の生涯を追った。春庭、宣長、門人たち、足立氏と彼の周囲の人びとの人生の「やちまた」(道がいくつにも分かれていること)を足立氏とともに追うような労作。足立氏と恩師や学友との交流の部分がとりわけ面白い。月イチ書評で取り上げました。https://www.kansai-woman.net/Review.php?id=2017402020/08/01
ジャズクラ本
15
◎これは司馬遼太郎が考えたこと13で触れられていた本。ただただ圧巻の凄い本である。著者の足立巻一氏が半生をかけて本居宣長の実子 春庭を徹底的に研究した、小説の体をなした研究書。単なる伝記に留まらず、春庭と関与した義門や平田篤胤他の事跡言論まで筆が及んでいる。自分で関心のある物事を調べるのは楽しいものだが、40年にも渡る他人の研究の子細を読むことがこれほど面白いとは新たな発見だった。著者の知的好奇心の充足感がそのままこちらに伝わってくる。まだ上巻が終わったばかり。下巻が頗る楽しみである。2019/12/16
はる
13
図書館本。いきつけの図書館の展示本コーナーで。テーマは「人生いろいろ」その面展台でこの表紙がこちらを向いていなかったら一生出会わなかった本だと思うので、まさに人生いろいろ。「やちまた」ということばが、分かれ道迷い込んだら…というのは何となく知っていたけれど。江戸の人達の暮らしや、昭和の初めの学生生活やらに一緒に迷い込んで行くとは。(文法はからきし駄目ダメの読者でごめんなさい)2016/10/03
isao_key
9
神宮皇學館(現皇學館大學)在学中、白江教授の文法学概論の授業で、本居春庭とその著書『詞の八衢』『詞の通路』を知り、本居宣長の長男であり、35歳で失明してしまった国語学者に興味を持つ。本書は、宣長全集、書簡集他、春庭に関して残された少ない資料を基に、ゆかりのありそうな地に赴き、人物像と業績を明らかにしようとした評伝。調査にかける情熱または執念はとても大学学部生のレベルではない。卒業後新聞社に勤めるが、足を使った調査の下地はすでに学生時代にできていた。発行まで40年の歳月をかけた大作は、また青春小説でもある。2015/06/23
-
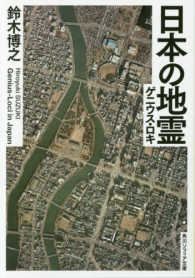
- 和書
- 日本の地霊 角川文庫