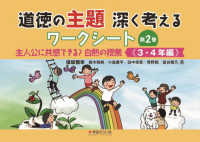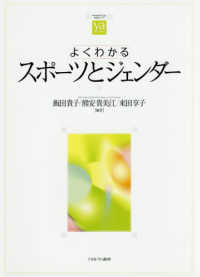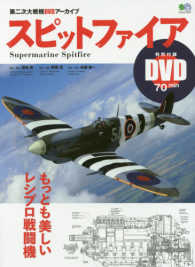内容説明
戦後日本最大の政治ドラマ、安保改定。首相として交渉の先頭に立った岸は、何を考え、どう決断したのか。改定準備から内閣退陣までを岸の肉声で再現する本書は、側近、政敵らの証言をも収録し、戦後政治の一つのクライマックスを重厚で濃密な政治過程として描き出す。オーラル・ヒストリーの先駆的な業績としても知られる、第一級の文献である。
目次
第1章 戦前から戦後へ
第2章 政界復帰、そして保守合同へ
第3章 政権獲得から安保改定へ
第4章 安保改定と政治闘争―新条約調印前
第5章 新安保条約の調印から強行採決へ
第6章 強行採決から退陣へ
第7章 思想、政治、そして政治家
編者補遺 インタビューから二十年、いま…
著者等紹介
原彬久[ハラヨシヒサ]
1939年(昭和14)、北海道釧路市に生まれる。1963年、早稲田大学第一政経学部政治学科卒業。東京国際大学名誉教授、法学博士(一橋大学)。日本政治学におけるオーラル・ヒストリーの先駆者。専攻は、国際政治学、日本政治外交史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nakagawa
8
岸信介に興味を持ったのは友達がよく岸信介という名を出してたからである。それまではただ名前を知ってるだけで中身は全く知らなかった。若い頃から秀才であり読書家でもあり学力、知力は政治家でも長けている方である。太平洋戦争、安保改定までまさに日本の激動の時代を政治家として送った人物だ。若い頃には北一輝の国家社会主義に傾倒しており、マルクスの著作は読んだそうだがあまり共感しなかったそうだ。総理大臣の後は憲法改正を心から願っていたが実現しなかった。左翼リベラルから特に嫌われているが、政治力と頭脳は長けているのは確か。2017/09/12
ぽん教授(非実在系)
3
最近古田博司先生が仰る「先見性・実用性・現実妥当性」というものは、我が国に於いては単なる平時に於いてのみ有能な官僚かもしくは害悪でしかない空想主義者が跋扈する中大半の人間には縁遠いものとなってしまっている。しかし本書の主人公岸信介は安保や改憲の必要性や巣鴨にいながらにして自由と民主主義を基礎とすべきことを見抜く先見性、有用ならば社会主義から計画経済や保険制度などで参考にする実用性、国家主義や権力の使い方を徹底的に考えた上で実際に行使していく現実妥当性に富んだ怪物である。その魅力はわかる人だけ味わえるのだ。2015/06/26
こと
2
大学のレポートのため読了。 岸信介に対して、あまり良いイメージはなかったが、ただイメージだけではいけない、知ろうとしなければいけないと感じた。イメージで人を判断してはいけないと感じた。 ある先生から岸信介についてお話を伺う機会があり、そこでより岸に対する勝手なイメージが晴れた。 近現代に関して、先入観を捨ててもう一度学び直してみようと思う。
hatohebi
2
「官僚」と「政治家」の違いについて本書で語られているが(42、459頁)岸自身その双方を経験した。官僚は結果の善悪に関わらず法律を遵守して事に当たるのに対して、政治家は「結果責任」でありよい結果のためには法律つまり国家の仕組みに手を入れることも厭わない。岸を含む戦前の「革新官僚」は、例えば満洲国のような壮大な実験場でそれが実現できた。そして自分の望む結果つまり「理想」の実現のためには、左右のイデオロギーに拘らず、最も実効性のある手段を取ることが必要だ(89頁)。この理想を岸は「見識」とも呼ぶ。2018/01/01
bassai718
1
安保改定時を中心とする生々しい証言が続いて面白い。終盤の政治家評も率直、適格で頭の良さを感じさせる。自身も再度の総理返り咲きを密かに考えていたそうで、「総理は一度やれば一丁上がりということでなく、しばらく野に下って国民の側に立って物事を観察し、これを前の経験と結び合わせてもう1度総理をやった政治家は前より大いに偉くなる」という記載に目が留まった。岸氏の孫である安倍晋三氏は、一度目の総理退任後、この本を読んで再登板の決意を抱いたのではないかと想像する。2017/12/18
-
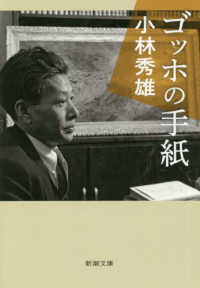
- 和書
- ゴッホの手紙 新潮文庫