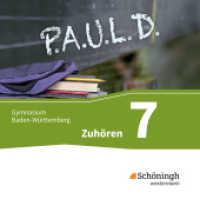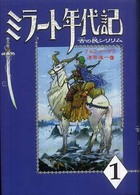内容説明
かつて数千年がかりで白く均一にした粒が、いまや不揃いで色付きのものこそ高額になる。塩の真価を定めるのが容易であったことは、いまだかつて一度もない。悪名高き塩税「ガベル」、ガンディー塩の行進、製塩業の衰退と伝統的職人芸の復活。塩からい風味にユーモアをそえておくる、博覧強記のノンフィクション。
目次
第2部 ニシンのかがやきと征服の香り(承前)(自由、平等、免税;独立の維持;塩をめぐる戦い;赤い塩)
第3部 ナトリウムの完璧な融合(ナトリウムの悪評;地質学という神話;沈みゆく地盤;塩と偉大な魂;振り返らずに;自貢最後の塩の日々;マー、ラーそして毛;魚より塩をたくさん;大粒の塩、小粒の塩)
著者等紹介
カーランスキー,マーク[カーランスキー,マーク] [Kurlansky,Mark]
1948年、米国コネティカット州生まれ。歴史や食物、海洋などに関するノンフィクションを中心に作家活動を展開。ニューヨーク・タイムズ・ベストセラーリストに数多くの著作が含まれ、世界二五ヵ国で翻訳されている。とくにCod;A Biography of the Fish That Changed the World(『鱈―世界を変えた魚の歴史』)はさまざまな賞を受賞するなど評価が高い
山本光伸[ヤマモトミツノブ]
1941年、東京生まれ。国際基督教大学歴史学科卒業。英米文学翻訳家、(株)柏艪舎代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Meme
12
実際に読んだのは文庫ではなく、ハードカバーです。ガンディーがお茶目な人だったこと、タバスコが塩に由来するものだったことなど目から鱗がたくさんありました。2024/01/20
to boy
9
下巻は北米、インド、中国での塩の歴史を衷心に記述。著者の博識にはおどろきです。この本を書くためにどれだけ多くの資料を読み込んだのだろう。塩漬けの肉、魚のように保存のために塩が利用されてきたが、缶詰の発明、冷凍技術の進歩によってその使命に変化が起こってきます。塩を求めて町が出来、塩税をめぐって反乱が起こる、そんな壮大な人類史が楽しめました。2014/11/09
もなおー
8
すっごく面白かった。話題が現代的な部分に踏み込んでくるので、我々にも身近な話もたくさん出てくる。マグロの話は心が痛い…2017/02/20
たびねこ
8
人間の道はもともと塩を探す動物が踏み固めた道の上につくられたもの。道の先には必ず動物たちの「塩なめ場」があり、それを後から来た人間が略奪していく。塩をめぐる人類の欲望に際限がない。歴史まで変えていく侮りがたい「塩の力」も興味深いが、塩漬け料理(レシピも付いている)の歴史に相当のページを割いているのも本書の魅力か。2015/02/09
tsubomi
7
2016.11.01-11.05:当初は製塩業を営んでいたマキルヘニー家が「タバスコソース」を作ることになった経緯、電気分解に成功したデーヴィーの功績、冷凍食品会社として有名になるゼネラルフーズの創業、WHOが食塩にヨウ素を添加するよう勧告していた件、中国人の好きなグルタミン酸ナトリウム、かつて世界中にいたチョウザメ、コサックが製造していたキャビア、ボラの卵から作るボッタルガ、世界の二大製塩会社カーギルとモートン、シチリアのケーパーとマグロと塩の関係、フェニキア人の塩とプロシュート(つづく)2016/11/05
-

- 和書
- 神との旅路