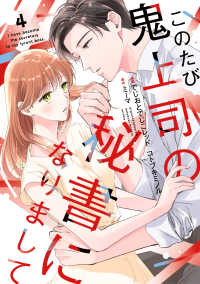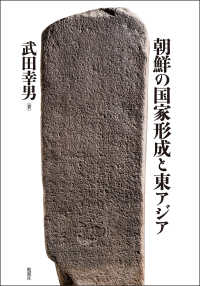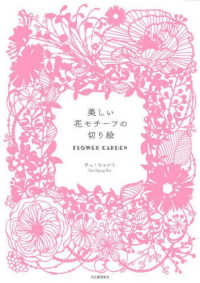内容説明
「多くの人にこの悲劇を知ってもらいたい」号泣した記者がいた。歯を食いしばってシャッターを切ったカメラマンがいた。―77人が極限の現場から伝える取材記録。彼らはその時、何を感じ何を考えたのか。震災から半年後に緊急出版して大反響を呼んだドキュメンタリーを文庫化。
目次
第1章 津波(孤立した公民館で43時間を過ごして;安否不明の妻と避難所で再会 ほか)
第2章 原発(震災翌日、第一原発の正門前まで近づいたが;生きていた証し、生きている証し ほか)
第3章 官邸・東電など(総理番として;首相の誤ったリーダーシップ ほか)
第4章 東京、千葉そして各地で(巨大都市・東京にもいずれ大地震は来る;東京・池袋であふれかえった帰宅困難者 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
キンモクセイ
57
77人の記者たちの渾身の手記。津波の章、原発の章、東電の章などにわかれている。読売新聞社では新人記者は地方局に配属される。家族を失って呆然としている人に「どなたが亡くなられたのですか?」なんてとても聞ける状態ではない。記者の使命か辛くても取材をしないといけない。辛い心情も伝わってくる。表紙の女性は世界中に有名になった1枚。ガレキの前に立ち尽くす姿。両親と妹と共に流された愛海ちゃんは彼女だけが助かった。「ままへ。いきているといいね おげんきですか。」この文字を読んで大号泣。そんな彼女も今は13歳なのか。2020/03/27
タカボー
11
3月だから東日本大地震のことを思い出しながら読もうと思っていたら、まさかのまた大地震。それぞれの記者たちが目にした耳にしたドキュメント。全校生徒の7割が死亡・不明の石巻市大川小。改めて自分の同級生の顔とか思い浮かべて、それが7割もいなくなると考えるとこの災害の悲惨さがよくわかる。また亡くなった夫の車から見つかった妻へのホワイトデーのプレゼントなど、切ない話もたくさん。悲しみや絶望を記事にするということ。被災者に対して話を聞いたり、カメラを向けることへの罪の意識も理解できる。2022/03/21
Hiromix
8
忘れてはいけない。風化させてはいけない。記者たちの震災の取材記録。生の声だからこそのなのか、それぞれの日記のような仕上がり。だからこそ残すべきなのかも。2014/06/28
sasha
6
全国各地から被災地へ取材に入った読売新聞記者77人の取材手記。東日本大震災の被害は、海千山千の新聞記者たちをもたじろがせた。多くのものを失った被災者たちに話を聞き、カメラを向けるのは辛かったであろう。それでも「伝えなければいけない」という思いが記者たちを突き動かした。限られた紙面から漏れた話もたくさんある。それをこうたってまとめるのもいいのかもしれない。だが、読売新聞って福島第一原発事故以前も以降も、原発推進なんだよな。ひとりひとりの記者はそれこそ真摯に取材したのだろうが、釈然としないものが残った。2014/03/13
OHNO Hiroshi
5
いずれ地震が来る。富山には立山連峰が守ってくれるから、と思っていたのに、2024年1月1日能登地震。東日本大地震の映像を見ていて津波でながされているのに、物が燃えて火が上がっていたり、高波の波頭ではなくて、するり、ものすごい勢いで、スピードで津波が来る。少しでも長く地震などの自然災害に遭遇しないことを祈る。運命。2024/03/27