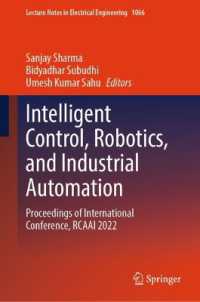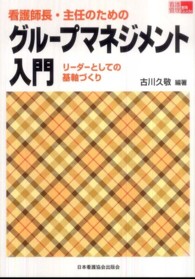内容説明
庶民から将軍様まで、物見高い江戸っ子たちにとって寺社は祈りと娯楽の場であった。茶屋から怪しげな見せ物小屋まで門前町で賑わう浅草寺。財政難の大名が賽銭目当てで屋敷内に祀った水天宮。地方名刹からご本尊を出開帳させ所場代を稼いだ回向院…等々。江戸で大人気だった寺社詣の実情を描く一冊。
目次
神田っ子の神様に朝敵のレッテル―神田神社と将門の首塚
お賽銭で稼ぐ大名屋敷―安産信仰で大繁昌の水天宮
金運の御利益で江戸っ子がフィーバー―虎ノ門金刀比羅宮と江戸の金比羅信仰
戊辰戦争をくぐり抜けた清水の観音様―寛永寺の清水観音堂と関東の清水寺
音楽と金運に蓮飯の味覚―江戸の行楽地不忍池の福神
人が集まる観音の寺、観音の町―浅草寺と浅草の町
一年を三日で暮らすお酉様―鷲神社と長国寺をめぐるお酉様信仰
神仏も相撲も興行する盛り場の寺―参詣か行楽か、二股かける回向院
成田不動尊が江戸に出張―深川不動堂と成田不動講の活動
新開地に咲いた王朝趣味の花―太宰府から江戸にやってきた天神様〔ほか〕
著者等紹介
鈴木一夫[スズキカズオ]
1935年生まれ。60年、出版社に入社し、社会科学分野の書籍編集に従事。86年、出版プロダクションを設立。90年頃より個人として、雑誌寄稿・書籍原稿執筆を開始する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。