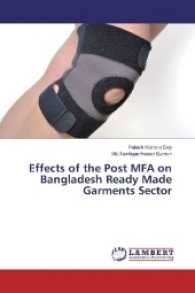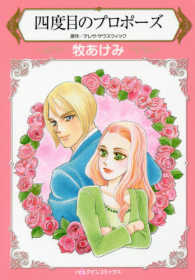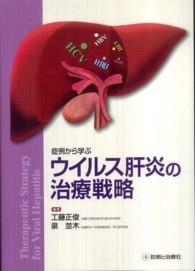内容説明
食べることには憂愁が伴う。猫が青草を噛んで、もどすときのように―父がつくったぶえんずし、獅子舞の口にさしだした鯛の身。土地に根ざした食と四季について、記憶を自在に行き来しながら多彩なことばでつづる豊饒のエッセイ。著者てずからの「食べごしらえ」も口絵に収録。
目次
ぶえんずし
十五日正月
草餅
山の精
梅雨のあいまに
味噌豆
油徳利
獅子舞
水辺
菖蒲の節句〔ほか〕
著者等紹介
石牟礼道子[イシムレミチコ]
1927年熊本県天草に生まれ、まもなく水俣に移住。小説家、詩人。谷川雁主宰の「サークル村」に参加して文学活動を開始。69年、水俣病問題が社会的に注目される契機になったと言われる『苦海浄土―わが水俣病』(第一回大宅壮一ノンフィクション賞、受賞辞退)を刊行。その後マグサイサイ賞や、93年には小説『十六夜橋』で紫式部文学賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
96
昭和ヒトケタ生まれ。「苦海浄土」は未読だが、熊本天草で高度経済成長前の地方農家における貧しいながらも生き生きとした生活を書いたエッセイ。この土地で大地と陽の光から生まれた野菜と新鮮な魚は、季節の豊饒感を表し、それを料理する両親の姿は子どもながらに体に染み入る記憶になる。魚をしめるのに厚手のフライ鍋で炒った焼き塩を使う父、志村ふくみ氏と京都で会った際に食べた鰹のたたきと備前焼風の深皿などが印象に残った。大都会で工業化された農産物を口にする度に、農の根幹を失った民族に胸が塞がれる思いがするとあとがきにある。2021/03/14
syaori
54
木の芽の香り、俎の音。食べることは様々な記憶と切り離せないもの。このエッセイでも、様々な食べごしらえの思い出は、春の草のような女衆のさざめきや襷の色の鮮やかさ、畑や摘み草の時に歌われた唄とともにある。そして、その華やぎは、家の没落を見た誇り高い父やそれに伴う苦労を偲んだ母にまつわる懐かしくせつない思い出や、「昔の百姓のおなご」のあわれを語る老婆の声などの上を風のように渡ってゆく。「ものみな稔る季節の豊穣感」と共に「躰のすみずみ、心の内側にのこっている」その憂愁は、食べることの貴さを何と豊かに伝えることか。2019/06/17
penguin-blue
50
毎年の季節の訪れや、心待ちにしていた年中の行事と深く結びついた、思い出すたび鮮やかな大切な食べ物の記憶。表現が難しいのだが、食というものがイベントのひとつでなく、かといって日々の単なる習慣や栄養補給でもなく、もっと暮らしの真ん中でどっしりとした存在感を発揮している。 そして「お米」の章、百歳のおばあさんから聞いた米作りの苦労の話、筆者の感想を差し挟まず、切り取られた生の言葉は意図的に作られた衝撃的なドキュメンタリーよりむしろ心を動かされる。巻頭の料理写真が地方色豊かで美しく、ぜひ実際に味わってみたいなあ。2018/07/22
紫羊
36
まず口絵の料理写真にびっくりした。すべて著者てずからの「食べごしらえ」だという、手間を惜しまず調えられた料理の数々。料理エッセイと括ってしまうのが憚られる唯一無二の豊かな語りを堪能した。池澤夏樹氏の解説も良かった。2018/05/20
ネギっ子gen
33
口絵はカラーで贅沢に16頁。豊潤な「食べごしらえ」の品々。正に眼福。食エッセーだが、著者は<美食を言いたてるものではないと思う。考えてみると、人間ほどの悪食はいない。食生活にかぎらず、野蛮さの仮面にすぎないことも多くある/食べることには憂愁が伴う。猫が青草を噛んで、もどすときのように>と書き、そこらの類書とは一線を画したものであることを、明確に宣言する。この父親にして、この娘あり。姑は妻が10歳の時に盲目になって発狂。それにも関わらず祖母を、父は<畏敬する人に接するようにものやさしく、丁重であった>と。⇒2020/10/24