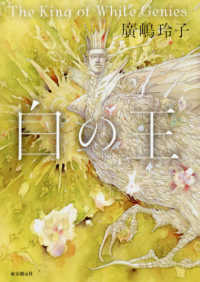内容説明
日本人と同じモンゴロイドの遠い枝分かれが、地球の対極で、16世紀以来の白人の掠奪と殺戮の果てに、いま絶滅の危機に追い込まれている。レヴィ=ストロースが名著『悲しき熱帯』の舞台となったブラジルを訪れて50年後、恩師の足跡をたどってこの地を旅した文化人類学者は何を見たか。最後の狩猟採集民ナンビクワラの現状にも接し、「なぜ熱帯は悲しいのか」を考える。
目次
1 反世界としてのブラジル(堆積する誇大妄想;歴史の気まぐれ ほか)
2 灰まみれのモラトリアム・ピーターパンたち(笛を吹く男たち;正座する女 ほか)
3 なぜ熱帯は今も悲しいのか(ヨーロッパ文明にとっての新世界;すべてを奪われた人びと ほか)
4 「紐文学」と口誦の伝統
5 私にとってのブラジル―十二年ののちに(“南蛮時代”の意味;ベニンと日本 ほか)
著者等紹介
川田順造[カワダジュンゾウ]
1934年東京生まれ。東京大学教養学部教養学科(文化人類学分科)卒、同大学大学院社会学研究科博士課程修了。パリ第五大学民族学博士。東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授、広島市立大学国際学部教授、神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科教授を経て、神奈川大学特別招聘教授、神奈川大学日本常民文化研究所客員研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
カネコ
4
◎ レヴィ=ストロース『悲しき熱帯』の舞台を約50年後(1984年)に訪れた著者の報告。単行本が上梓されるのはその約10年後(1996年)なので、その間の情報もある程度フォローされている。読者としてはナンビクワラの人たちの現在(2012年)が是非知りたくなる。文庫版あとがき(2010年)では、レヴィ=ストロース逝去前後の様子と、彼の生誕百年を政治利用しようとしていたサルコジのエピソードも。2012/07/02
梅子
1
『悲しき熱帯』読了者は必ず読むべき1冊。暈されて具体的に知る事ができなかった"未開"ではないブラジル社会の特異性をまず教えてくれる。ナポレオン戦禍を逃れてポルトガルが王室ごとブラジルに亡命していたこと、コントの人類教がブラジル革命の指導者を導いていたこと、奴隷だった黒人達がアフリカの憑依儀礼をブラジルにもたらしたこと…。母性と暴力が併存する社会の、内的欲望の発露と歪な外圧とに晒され、虚構の豊かさに甘んじている原住民の姿を「悲しき熱帯」と一言で表現したレヴィ=ストロースの、虚ろな眼差しが迫ってくるようだ。2023/01/18
人民の指導者
1
ブラジル、そしてブラジルのインディオは我々近代資本主義文明全体の「鏡」である。本書では、インディオの暮らしやブラジルの社会事情が蟻の目から親しみやすく語られ、そして鳥の目から我々の文明や学問全体を見据えて、平穏に暮らすインディオを取り込む、近代資本主義の「開発」と「経済合理性」という「幸せ」が描かれる。著者の「メタ・サイエンス」としての人類学者という立場には共感させられた。現代世界がどのような構造をしているか、実はこの本はその「見方」を上手く提供してくれるのではないか。好著。2011/06/14
冬月
1
個人のうちに、あるいは関連する他の個人との間に、意識の亀裂やわだかまりがまったくない、つまり素直に幸せに生きられた時間は、生そのものではあっても歴史になりえないのと同じように。だから歴史を必要つする社会は、たとえば王が王でないものを支配し、その支配を過去も参照しながら正当化する為に、過去についての語りを必要とするような社会だ。過去の意識化と、それについての語りを必要としない社会は、人々がまさに彼らの生活を、亀裂やわだかまりなしに生きている。2011/04/07
yagian
0
本文もよかったけど、あとがきのレヴィ=ストロース先生の最期についての話も印象的。サルコジに国葬されたくなかったというのはよくわかるな。2011/09/16