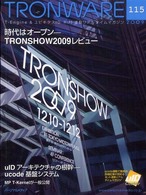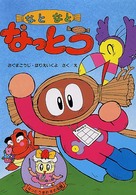出版社内容情報
香港でペストが大流行。命懸けの調査でペスト菌を発見する柴三郎。一方、東大閥との争いと様々な思惑の中、北里は「伝研」を失う。〈解説〉大村 智
内容説明
帰国した柴三郎は、福沢諭吉の支援を得て、困難を乗り越え、伝染病研究所の設立を果たす。そんなとき、香港でペストが大流行との報が。多数の感染者を出す生死をかけた調査でペスト菌を発見する柴三郎。その一方、東大閥との争いも激化。政治の思惑にも巻き込まれ、北里は「伝研」を失うことになるが。
著者等紹介
山崎光夫[ヤマザキミツオ]
1947年福井市生まれ。早稲田大学卒業。放送作家、雑誌記者を経て小説家に。1985年『安楽処方箋』で小説現代新人賞を受賞。医学・薬学関係に造詣が深い。1998年『薮の中の家―芥川自死の謎を解く』で第十七回新田次郎文学賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
長岡紅蓮
8
伝染病研究に尽力した北里柴三郎先生。上巻でも思ったけど、人脈が凄いなあ。福沢諭吉、志賀潔、森林太郎(鴎外)。更には黄熱病研究で知られる野口英世が伝染病研究所に入所していたことを初めて知りました。 上巻に比べて、年齢が行っているのもあるけれど人間味ある姿が印象的。 天国から北里先生は、コロナウイルス感染症に苦しむ世界をどのように見ているのでしょう?2020/04/15
ロボット刑事K
7
敬称略。コッホを始め、志賀潔、北島多一、野口英世等、北里柴三郎を取り巻く細菌学のパイオニア(野口英世?)、更に脇を固める福沢諭吉、森鴎外等々歴史的人物のオールスター総出演です。肥後もっこすと言えば聞こえはいいですが、北里は随分と扱い難い為人だったみたいですね。また、若い芸者を囲っても悪びれずに男の甲斐性とは、しみじみ時代を感じさせますなあ。多少の紆余曲折は経ても、彼の人生はつくづく幸運に恵まれたものだったようです。勿論本人の不断の努力あってこそでしょうけど。☆4つ。やはり私は彼を尊敬してやみません。2023/01/24
うろたんし
5
新紙幣に北里柴三郎が載ると知り、読みかけていた下巻を紐解いた。大村智先生が解説文を寄稿している。論語から「子曰徳不孤必有隣」を引いていて、ほんまにその通りやなあと感心する。本文中に、19世紀は微生物の時代と書かれてあった。20世紀はなんだろう、21世紀は。僕は、どうやって貢献するのだろうか。2019/04/10
うたまる
4
留学以降の活躍を描く下巻。国内では研究だけでなく経営、教育、政治に奔走させられる。そのイライラが溜まっての雷(ドンネル)だろうが、後で「つい言いすぎた」と謝る姿が愛らしい。それが彼の人徳なんだろうね。さて下巻で最も印象的なのは、経営のため特許取得を勧められた際のこの言葉。「確かに、特許を取ってしまえば、大きな利益があげられるはずだ。だが、わたしの研究はわたし個人のものではない」。終生、国に尽くす姿勢がブレなかった柴三郎が格好いい。この場面、LEDでノーベル賞を取ったあの人の不満顔がちらついて仕方なかった。2016/07/06
yuka_tetsuya
3
下巻は後ろ盾を失い、権力の陰謀に破れながらも、多くの人の助けを借りて北里研究所を設立し、さらに慶応義塾大学医学部や日本医師会の礎を築いた半生を描いている。ドンネルを落としても、その後のフォローを忘れない気配りが、有能な研究者を育て、集めたのであろう。「権力の太鼓持ちになるな、学問の壁と取り払え、研究は最終的に患者に恩恵を与える実学でなければならない。」など医学関係者なら必ず心に留めておかなければならない生き方の手本である。2013/04/07