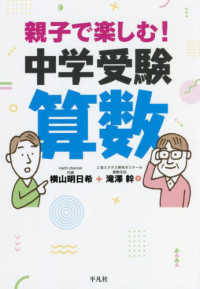出版社内容情報
生の暗さを凝視する地獄の思想が、人間への深い洞察と生命への真摯な態度を教え、日本人の魂の深みを形成した。日本文学分析の名著。〈解説〉小潟昭夫
内容説明
魂の原点。「地獄」を通して日本人の精神を探る。
目次
第1部 地獄の思想(地獄とはなにか;苦と欲望の哲学的考察(釈迦)
仏のなかに地獄がある(智〓(ぎ))
地獄と極楽の出会い(源信)
無明の闇に勝つ力(法然・親鸞))
第2部 地獄の文学(煩悩の鬼ども(源氏物語)
阿修羅の世界(平家物語)
妄執の霊ども(世阿弥)
死への道行き(近松)
修羅の世界を超えて(宮沢賢治)
道化地獄(太宰治))
著者等紹介
梅原猛[ウメハラタケシ]
大正14年(1925)、仙台市に生まれる。京都大学哲学科に入学、学徒兵として召集され、戦後復学。昭和23年卒業。立命館大学教授、京都市立芸術大学教授・学長を経て、昭和62年、国立国際日本文化研究センター初代所長に就任(平成7年退官・現顧問)。平成13年より、ものつくり大学総長。『隠された十字架』(昭和47年、毎日出版文化賞受賞)では、法隆寺と聖徳太子の関わりを、『水底の歌』(昭和48年、大佛次郎賞受賞)では、柿本人麿の流罪刑死説を展開。その思索の範囲は哲学から文学、宗教、歴史と広範多岐にわたる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。