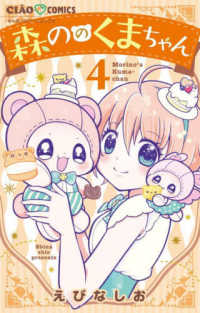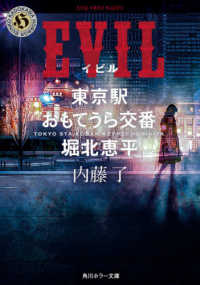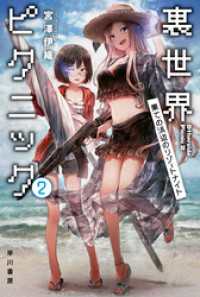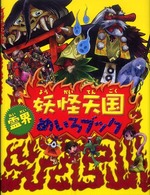出版社内容情報
「役者の一生」など芝居についての論考をまとめたもの。折口信夫芸能史の中核に当たるものであると同時に、著者の芸能に対する心情が伝わってくる作品集。
内容説明
「なまめける歌舞妓びとすらころされて、いよゝ敗れし悔いぞ身に沁む」(昭和二一年)と詠んだ折口信夫は、戦中から戦後、歌舞伎について度々論ずるようになる。防空壕の中で死んだ中村魁車、上方歌舞伎の美の結晶実川延若、そして六代目尾上菊五郎。役者論を軸に、豊穣な知とするどい感性で生き生きと描く独特な劇評集。
目次
歌舞妓芝居後ありや
役者の一生
市村羽左衛門論
実川延若讃
街衢の戦死者―中村魁車を誄す
戞々たり車上の優人
日本の女形―三代目中村梅玉論
宗十郎を悼む
実悪役者を望む
菊五郎の科学性〔ほか〕
著者等紹介
折口信夫[オリクチシノブ]
明治20年(1887)、大阪木津に生まれる。天王寺中学を経て国学院大学卒業。のち国学院大学教授、慶応義塾大学教授。昭和23年、日本学術会議会員に選ばれた。古代研究に基を置いた学問の領域は広く、国文学、民俗学、国語学、宗教学、芸能史にわたって独自の学風を築いた。昭和28年9月没。没後、全集にまとめられた業績により芸術院恩賜賞を受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
5
大阪で子供時代から女性に囲まれ、歌舞伎・浄瑠璃を観てきた通人的な同時代史的観点、男性の役者(女形も)の所作の色気を分析する同性愛的とされる観点、出雲大社の巫女だった阿国が始めたこの芸能への民俗学的観点・・・著者のこれら3つの観点が相俟って、本書は変幻自在な「かぶき」エッセイの集成となったようだ。「かぶく」=傾く=過度に逸脱する外連味(ケレンミ)を表現するように、十五世市村羽左衛門の贔屓や実川延若の所作の執拗な記述にも、社会から逸脱した異人たちの来訪という社会の日常の境界が破れる際の芸能の熱狂が仄見える。2025/03/22