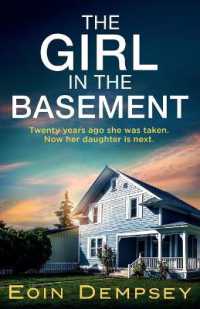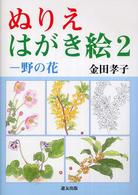内容説明
不断の向上心と強靱な精神力でつねに新たな分野へと向かっていった戦後最大の「社会派」大衆作家、松本清張。「人は他人の経験を知りたがっている。私のことを語らねばならない」―生い立ちから小説論まで、清張作品の背後にあるものが見えてくる名随筆を収録。
目次
学歴の克服
実感的人生論
私の中の日本人―松本峯太郎・タニ
碑の砂
ほんとうの教育者はと問われて
朝の新聞
かなしき家の長たち
瑠璃碗記
ハバナへの短い旅
暑い国のスケッチ
南北で会った女
あのころのこと
『西郷札』のころ
舞台再訪―『点と線』
私の小説作法
灰色の皺
私の黒い霧
小説に「中間」はない
私のくずかご
著者等紹介
松本清張[マツモトセイチョウ]
1909年、福岡県北九州市小倉に生まれる。51年、『週刊朝日』主催の“百万人の小説”で「西郷札」が三等に入選。53年「或る『小倉日記』伝」で第二八回芥川賞を受賞。55年、短編「張込み」で推理小説に進出し、56年に作家専業となる。58年に刊行した初の推理長編『点と線』は大ベストセラーになり、一大推理小説ブームを引き起こす立役者のひとりとなった。70年『昭和史発掘』で第一八回菊池寛賞、90年朝日賞受賞。92年永眠
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おさむ
33
松本清張の雑文集。表題作を含む自らの来歴を語ったものが興味深い。父母共に小卒で、浮き沈みが激しい人生。極貧の暮らしも経験し、自らも高等小卒から転職を重ねた。朝日新聞西部本社に雇員として働いていた40歳の時。応募した小説「西郷札」が入選し、たまたま雑誌に掲載された。それがきっかけで小説家の道に。「全ては運が良かったから」と本人は謙遜しているが、やはり小卒の学歴という劣等感をバネに地道な努力を重ねた成果でしょう。常に低い目線で書き、社会性を失わなかったのが、今なお人気の絶えない理由だと確信しました。2019/03/24
kazuさん
32
松本清張には《半生の記》という自伝的小説があり、その内容が「実感的人生論」の項にまとめられています。清張は、「日々の生活の中で感情に流されて自分を見失うことを最も警戒すべきだ」と語っています。どんなに苦しいときでも、自分の中に誇りを持ち、今の自分を少し離れた視点から冷静に見つめることが大切だと説いているのです。これは、清張自身が底辺の生活を経験したうえで紡ぎ出した、実感に裏打ちされた人生論であると感じました。 2025/10/21
旗本多忙
22
既読にはしてないが、松本清張作品は、若い時分によく読んだ。誰もが知る推理の王道、点と線、時間の習俗、歪んだ複写、砂の器からゼロの焦点などなど有名所だ。本は好きだったが、田舎だったので、学校の図書室は単行本が殆んどで、私が文庫本を知ったのは中学校を出てからのようだ。安いのと持ち運びが楽で文庫本がメインになった。それはさておき、本書は松本清張の人生(学歴とか家庭環境など)の一端が見える小論である。薄い本だがかなり日数を要した(笑)私は時代小説家をこき下ろした江戸学の三田村鳶魚の項が面白く、へらへらと笑が出た。2023/03/27
浅香山三郎
17
清張さんの随筆などを中心にまとめたもの。Ⅲ・Ⅳ章で、自身の作家としての歩みや文学観、菊池寛作品への親しみなどをざつくばらんに述べ、一種の藝談を聴いているやうな愉しさがある。メインは昭和40年代の作品ばかりで、あれだけ小説を連載しているなかで、よくもこれだけ脇の仕事もしていたのだなあと思ふ。2021/03/21
ヴァン
13
作家、松本清張の自伝的エッセィ。頼る師もなく独学で人生を切り開いた清張の文学観・人生観を綴った平易な叙述で、小説でお馴染みの独特な文章スタイルも楽しめる一冊になっている。こういう作家はもう出ないだろう。清張に不案内な人にもおすすめしたい。2017/10/31