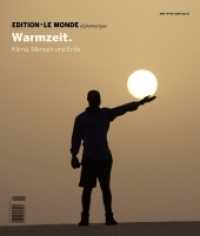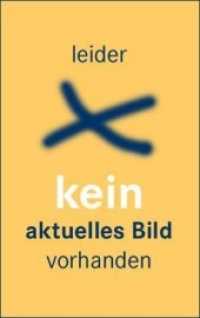内容説明
光仁・桓武父子の登極によって安定をとりもどした皇室は征夷に力を注ぐ一方、千年の都平安京を作り出した。そして詩宴・仏事・歌合と王朝絵巻をくりひろげる間に、地方では浮浪人が続出し、藤原氏は徐々に権力を高めていく。律令体制崩壊の過程を壮大に叙述。
目次
女帝没後の政局
桓武天皇の登場
征夷大将軍坂上田村麻呂
平安京の建設
平城上皇の変
内裏・院・神泉苑
最澄と空海
王朝の詩人たち
応天門の炎上
関白藤原基経の執政
多恨の歌人在原業平
受領と郡司・百姓の抗争
時平と道真
古今の時代
東の将門と西の純友
天慶年間の大乱
天暦の治
天皇親政の終焉
著者等紹介
北山茂夫[キタヤマシゲオ]
1909年(明治42)、和歌山県に生まれる。1934年(昭和9)、東京帝国大学文学部国史学科を卒業。立命館大学法学部教授、同大文学部教授を経て、1969年以後文筆活動に入る。専攻は日本古代・中世史。万葉集を歴史史料として評価・活用する研究法を切りひらく。1984年、逝去
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
44
北山先生の本はどちらかというと平安時代ではなく、万葉の時代を書いておられるのが多く私も昔それらの本にかなりお世話になりました。この本は平安時代についてかなり分析をしておられていて、地方の豪族たちが力を蓄えて京都でのんびりしている天皇家や藤原家に対して、徐々に反乱などを起こすような状況になっています。ちょうど塩野さんのローマ人の時代の「終わりの始まり」を読んでいるような感じになりました。また最澄と空海についての個所も参考になりました。2015/04/05
てつ
39
まだ4巻だけど、実に面白い。筆者によって多少筆致や史料の扱い方は違うが、個々の歴史事象を丹念に説明している。長いから当たり前なのだが、一般人にもわかるように根拠をせいりしている。50年近くもベストセラーなのがわかる気がする。2020/09/27
柏もち
11
この時代に魅力的な人物が出てこないので、あまり面白くなかった。怨霊に懲りたのに繰り返す政治疑獄、早めの引退で上皇になっての放蕩生活、藤原氏の外戚政治…と政治面の繰り返しが多いように感じた。天変地異が多く、百姓は辛苦に喘ぎ、地方豪族や受領たちばかりが私腹を肥やしていて、国府の地方に対する執行力も低下して、あまりいい時代じゃない。本書は庶民の生活や仏教、歌文化など、幅広い分野までカバーしている。2016/04/17
あしお
7
順調に読み進めている「日本の歴史」若い頃に読んだ本の再読なんだけど、やはり大学生と50のオヤジでは理解力も問題意識もだいぶ違うようです。地方の実情について興味深く読みました。今の自分が「このど田舎でどうやって生きていこう」と考えているせいでしょう^^;。昔より個々の人物の内面を想像できるようになってました。平安時代というのはなんというか心理戦の様相ですね。。良二千石という単語が気になりました。つまり立派な地方行政官を指す言葉なんだけど、いつの時代もこういう人は少数でもいるもんですね。2020/06/26
河童
7
古代律令制が変容したというかひずみが見え始めた平安初期、末端の国民は重税感に苦しんだのではないだろうか。承平・天慶の乱の背景にはそのような社会背景が感じられる。一方で国風文化が栄えたというのだけれど、庶民には文化などに勤しむ余裕はなかったでしょう。空也が支持されたのも決して平安ではない世情を示している気がする。解説で指摘された通り国際関係の記述が少ないのは残念。2019/02/05