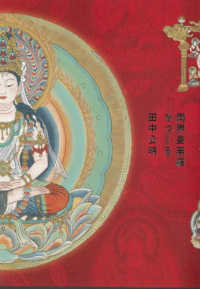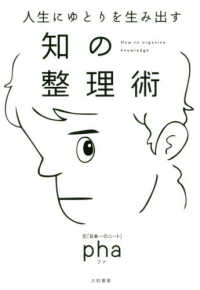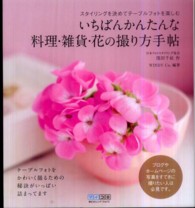内容説明
唇でふれる唇ほどやわらかなものはない―その瞬間、二人の絶望的な放浪が始まった。詩集『こがね虫』で詩壇にはなばなしく登場した詩人は、その輝きを残して日本を脱出、夫人森三千代とともに上海に渡る。欲望と貧困、青春と詩を奔放に描く自伝。
目次
発端
恋愛と輪あそび
最初の上海行
愛の酸蝕
百花送迎
雲煙万里
上海灘
猪鹿蝶
胡桃割り
江南水ぬるむ日
火焔オパールの巻
旅のはじまり
貝やぐらの街
著者等紹介
金子光晴[カネコミツハル]
明治28(1895)年、愛知県に生まれる。早大、東京美術学校、慶大をいずれも中退。大正8年、『赤土の家』を出版後渡欧、ボードレール、ヴェルハーレンに親しむ。大正12年、『こがね虫』で詩壇に認められたが、昭和3年、作家である夫人・森三千代とともにふたたび日本を脱出、中国、ヨーロッパ、東南アジアを放浪。昭和10年、詩「鮫」を発表以来、多くの抵抗詩を書く。昭和50(1975)年没
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HIRO1970
74
⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎リハビリ25冊目。旅紀行物のルーツとも言えるどくろ杯。金子さんはお初です。先日亡くなった私の祖母の生年である1920年の関東大震災から物語は始まります。著者はこの100年前からの自伝を40年後に回想して3部冊にしています。(まだ2冊もあるのでかなり嬉しい!)本書では今のバックパッカーが言うところの沈没を上海、香港、シンガポールで繰り返しながら巴里を目指します。本や絵を同胞に売り捌き生活の糧を得て次の目的地までの旅費を工面する。当時の風俗史としても圧巻の内容で類を見ない一級品でした。 2019/09/13
こばまり
58
この逃避行に殆ど憧れを抱いてしまう。より雰囲気を味わいたくて、多く流布する晩年のものでなく若き日の筆者の写真を眺めつつ読む。「…ほんとに、そうね。」自室で夕暮れ時、声に出して相槌を打った己に驚く。2018/08/04
syaori
57
語られるのは、7年にわたる「めあても金もなし」の作者の「欧州船旅」の前段。その発端は、関東大震災を契機にした当時の鬱屈した社会情勢と若さの「偏見と無惨」に満ちている。女学生との恋愛と妊娠、結婚、若い自意識と「貧乏の惨憺たる苦味」が覆う毎日と。しかし、その「性と、生死の不安の底につきまぜた」「酸っぱい人間臭」のする生活や旅からは鈍い焔が揺らめくよう。「泥沼の底に眼を閉じて沈んでゆく」ような日々の一体どこからこの煌びやかなものが現れるのか。ただ、それに目を奪われた自分は、もうこの旅に付き合うしかないようです。2019/06/05
zirou1984
52
明治から大正、昭和を生きた反骨の詩人による回想録、という枠を超えた言葉の爆弾。立て板に汚水とでも言うべき放蕩と貧困の生活を続け、金策の当てもなく妻と上海へと渡るその様相だけでも相当の無頼振りなのだが、それを表す言葉の数々がもう破格なのだ。著者の前では人間というものが等しく体液に塗れた糞袋として見えていながら、その内側から詩情というものは立ち昇っていることを決して見逃さない眼差し。困難な日々という泥沼の底に沈んていく人間性がぼろぼろとこぼれ落ちている。生きるって何だろう。きっとこういうことなんだろう。2016/02/09
chanvesa
32
この本を読んだ方の感想を読んで、なるほどと思いながらも、やはり私にはこの高い湿度というか、さらけ出された自身のねっとりした肌あいがいやになってくる。思えば、この本は中学何年かの時に、中国に関する本を読んで感想を書く課題が出て、尊敬する国語の先生に相談したところこの本を貸してくれた。十数頁で断念。結局、親が貸してくれた東洋文庫の古代中国寓話集かなんかを読んでごまかした。それ以来、この本が気になっていた。読んだものの自分に合わなくて、今になってあの国語の先生はなんなんだ、中坊にこれを読ませるかとあきれた。2015/12/18