出版社内容情報
〈私〉についてこうして書いている〈私〉という存在とは…。〈私〉と世界との関係を見つめた表題作はじめ、思考のかたちとしての九つの短篇小説。〈解説〉新宮一成
内容説明
“私”についてこうして書いている“私”という存在は、いつか“私”がいなくなったあとにかつていた“私”を想起する何者かによって“私”の考えをなぞるようにして書かれた産物なのかもしれない…。表題作をはじめ、「写真の中の猫」「閉じない円環」など、“私”と世界との関係を真摯に見つめなおした、九つの思考のかたち。
目次
写真の中の猫
そうみえた『秋刀魚の味』
祖母の不信心
十四歳…、四十歳…
あたかも第三者として見るような
閉じない円環
二つの命題
“私”という演算
死という無
著者等紹介
保坂和志[ホサカカズシ]
1956年生まれ。早稲田大学政経学部卒業。90年、『プレーンソング』でデビュー。93年、『草の上の朝食』で野間文芸新人賞、95年、『この人の閾(いき)』(新潮文庫)で芥川賞、97年、『季節の記憶』で谷崎潤一郎賞と平林たい子賞を受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しゅん
18
再読。先日、直接保坂さんの話を伺う機会があったが、本当にこんな風にしゃべる人なんだな。この本は要約するのがひたすら難しくて、それは論の結論だけを取り出すと全然面白いものにならず、言葉が連なっていく流れ自体を知らないとなにもわかったことにならないからだ。という内容のことが「祖母の不信心」の中で書かれてます。近代的な教育を受けたわけでもない田舎育ちで、仏壇に手を合わせることに対して「よくもまぁ、毎朝そんなことするなぁ」と言ったというおばあさん、会ってみたかったなぁ。2017/08/09
しゅん
11
何故、これが小説として成立してしまうのだろうか。猫の写真、小津『秋刀魚の味』、不信心な祖母の記憶などをきっかけに展開される思考の流れを追うだけなのに、「エッセイ」という言葉には不釣り合いな重さが感じられる。死や時間などの終わりのないテーマを扱っているからか。それもあるかもしれない。だが、死について書いたからといって重厚な文章になるとは限らない。迂回を続け、断定を避け、それでも並んだ言葉は生の条件の臨界にまで触れる。一体、何故こんなことが…。疑問は深まるばかりだし、驚嘆は増すばかりだ。2017/04/17
ぽち
8
ようやく引っ越しが終わったのだけど(荷ほどきが済んだ、とは言っていない)、卒倒寸前のドタバタの最中に読んでいた、というシチュエーションであった、にしてもこれまでに読んだ保坂さんの著作の中でもかなり難解で、行きつ戻りつして、そのようにしてもなかなかに把握、捕捉できない、論はうねうねと進み、夾雑物がまとわりつく、いやそれらはすべてつながっている?等価にある(これはわたしの世界観であるか)記憶が「私」を規定するか?そのリアリティは? 2023/07/03
giant_nobita
5
オチが投げっぱなしな話が目につく中途半端なエッセイ。「時間がこの世界に残らないで消えてしまう」ことにしても、「この世からいなくなる」ことと「ぼくが生きている」こととの繋げ方にしても、もとより答えの出ない問いを巡って書かれているのだが、暫定的な結論で文章をまとめないことを誠実さと勘違いしているような気がして、スリリングさが感じられない。「二つの命題」におけるアウグスティヌスの話は同じ作者の『小説の自由』のほうが深められているので、そこに至るまでの試行錯誤の跡として読めば保坂ファンは楽しめるかもしれない。2016/11/28
おいしい西瓜
4
保坂和志の著作を読んでいると同じ話題が繰り返し登場するけれど、それは悪いことではなくて、まぁ良いことと断言するようなことでもなくて、ただ特徴的だなぁと思う。それはよく話す友人が全く同じことを時を空けて何回も話すようなことで、最初の何回かは引っかかったり突っ込みを入れたりするけれど、ある一定以上からはその人の個性の一つとして数えられるようになるというようなことで、そういう意味で保坂和志は話すように書いている。それがなんだか心地よくて、話している内容がなんであれ面白いと思って読むし、読めるからいい。2025/07/10
-

- 電子書籍
- 無能な継母ですが、家族の溺愛が止まりま…
-

- 電子書籍
- Retry~再び最強の神仙へ~【タテヨ…
-

- 電子書籍
- シャーリー 私を守る君を、守りたいから…
-

- 電子書籍
- 宝石の国(8)
-
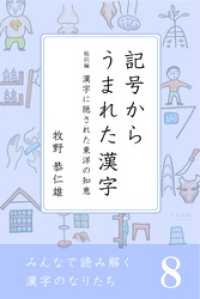
- 電子書籍
- みんなで読み解く漢字のなりたち8 記号…




