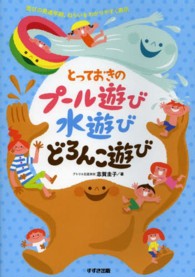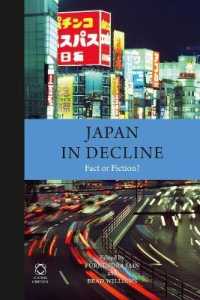出版社内容情報
少子化から教科書問題、テロまで、社会のすべての問題は、戦後日本の「都市化」=「脳化」とその行き過ぎにある―われわれの生き方を根本から問い直す「時評を超えた」最新時評集
内容説明
元来、人間にかかわることは面倒にきまっている。けれども、「ああすればこうなる」式の考え方に慣れた日本人にとってすべては論理と理屈。一寸先は闇ということさえ忘れている。あの事件、この出来事から語られる、現代人に取り憑いた重い、おもーい病い。果たして、あなたの脳は大丈夫だろうか。
目次
「都市主義」の限界
日本人の「歴史の消し方」
「少子化」は問題なのか
情報社会の「人間の幸福」
「田舎暮らしブーム」を考える
「子どもの問題」を考える
そもそも歳をとるとはどういうことか
「考えているかどうか」を考える
現代社会の思想と医療
マニュアル時代と倫理〔ほか〕
著者等紹介
養老孟司[ヨウロウタケシ]
1937年鎌倉市生まれ。東京大学医学部を卒業後、解剖学教室に入る。東京大学大学院医学系研究科基礎医学専攻博士課程を修了。95年東京大学医学部教授を退官。96年より北里大学教授。89年、『からだの見方』でサントリー学芸賞を受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
空猫
21
お気に入りさんのレビューから。「都市主義の限界」の改題。'98年~のエッセイなので少しだけ時代を感じる、けれど何も変わっていないとも。養老先生もおいらが日頃モヤモヤしている気持ちを的確に言葉にして下さる方だ。天災の被害、公共の場の事故に「誰の責任!?」と言う人の考え方、高学歴なのに簡単に洗脳された理由、現代社会で子育てや老人が問題になるのは…全ては都市(脳)化が鍵なのだ。読んでいて膝打ちまくり、色々と腑に落ちてスッキリ。2019/12/11
中年サラリーマン
18
著者の「唯脳論」の噛み砕いた版か。始めからそこにあるのでしょうがない「自然」に対し「都市」は人間の造り出したものである。故に造り出すためのデザインがあったはずだ。その場所は脳であろう。よって「都市」は脳から生み出されたといえる。つまり都市民は脳の中に住んでいるのである、というもの。都市は創り出した物だから「しょうがない」では済まない。創造した責任者を探そうとし暴走しかねない。よって、都市機能を守るために制度やマニュアルが存在する。著者の考えに賛成反対はあるだろうけど、僕は面白い事考える人だなぁと思った。2014/03/27
うえ
4
「社会は私の考えでは脳が作り出すものである。アリの社会と呼ばれるものであれ、チンパンジーの社会であれ、それを脳が作り出すことは疑いえない。多くの生物学者は遺伝子が基本だといまでは考えている。だから米国で論じられる社会生物学やとくに進化心理学では、社会の問題を遺伝子に還元しようとする傾向が強い。それは短絡である…実際にやってみなくても、小さいとはいえアリの脳を変更すれば、個体であればその個体は巣から排除される。遺伝子をいじって、巣全体の個体の脳を変えれば、全体の行動が変化するにちがいない」2017/03/05
晴間あお
1
元の単行本の発刊が16年前。しかし時事の用語が古いだけでぜんぜん色褪せていない。脳化はますます進行し「ああすればこうなる」式の考え方は強くなっているように思う。ボタンを押せば意図した結果が得られる。いまスマホにはボタンすらない。どこをタップしたらどうなるか、その繋がりに身体性はない。脳化とゲーム化は似ている気がする。「努力が報われる社会」と聞いたときゲームを想像した。敵を倒せば経験値が貰えてレベルが上がる。そう社会をプログラミングせよという話しなのではと。アニメが流行るのも脳の産物だからだったりして。2018/09/20
konomichi
1
医学者による頭脳論かとおもいきや、養老先生かあちこちで書いたエッセイを集めたものに勝手にタイトルつけたもの、だった。とはいえ、示唆に富んだ話も多く、とくに「対象か方法か」というものの見方には目からウロコ。お年寄りの世間話に付き合う感じで読むと意外と得るものは大きいと思いますよ。2017/09/09