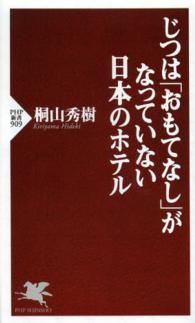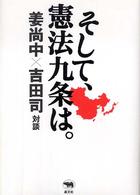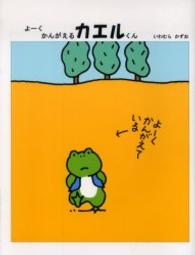出版社内容情報
無為な人生を送ってしまう原因の一つは死の否認である。明日があると思ってやるべきことを先延ばしにする人間は成長しない。好評「死ぬ瞬間」続編。
内容説明
人が目的のない虚しい人生を送ってしまう原因の一つは、死の否認である。永遠の命を持っているように生きていると、やるべきことを先延ばしにしがちだからだ。死を意識することによって、人間は最後の段階まで成長する―。死とその過程をめぐる問題を、末期患者や医療現場からの声をもとに考察する。
目次
1 序説
2 どうして死ぬことはこんなにも難しいのか
3 他の窓から見た死
4 死ぬことは易しいが、生きることは難しい
5 死と成長―ありえない組み合わせか?
6 死、それは成長の最終段階
7 結び
著者等紹介
キューブラー・ロス,エリザベス[キューブラーロス,エリザベス][K¨ubler‐Ross,Elisabeth]
精神科医。1926年、スイスのチューリッヒに生まれる。チューリッヒ大学に学び、1957年学位を取得。その後、渡米して、ニューヨークのマンハッタン州立病院、コロラド大学病院などをへて、1965年、シカゴ大学ビリングズ病院で「死とその過程」に関するセミナーを始める。1969年に『死ぬ瞬間』を出版して国際的に有名になる
鈴木晶[スズキショウ]
1952年東京生まれ。東京大学文学部ロシア文学科卒業、同大学院人文科学研究科博士課程満期修了。現在、法政大学国際文化学部教授。専攻は文学批評、精神分析学、舞踊史
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kanaoka 58
9
続・死ぬ瞬間。医師である著者は、その後臨死体験から輪廻思想に絡み取られていく。本書にもその前兆が多数見られる。社会的隠蔽状態にある死を直視し、死期において環境をどう整えるべきかという点には共感が持てるが、人生が成長を目的とするものとし、死をその文脈で意味付ける姿勢には、西洋進歩的価値観や自己意識の束縛を感じざるを得ない。死の意味、人生の方向性・目的を確立する事は、精神の安心・満足という束縛に囚われる事であり、突き止めていけば輪廻思考にも行き着く。精神に嵌るのではなく、精神そのものを見守るべきであろう。2016/01/24
すうさん
4
キューブラー・ロスの本は本書で4冊目。本書でも、書かれている厳しい現実とは裏腹に、読後はいつも静かでおごそか光に包まれる。私自身死に対して達観した訳ではないが、恐怖は感じなくなっている自分に気づく。それと同時に「残りの命をどのようにして生きるのか」を考えている自分にも気づく。「死」を考えることは「生」を考えること。そうして「死ぬこと」そのものより「死んでいく状態」に苦しめられること。しかし自分自身はもちろん自分の周囲の「喪失」体験こそが、人生最大の「学び」になることなど。実体験からくる哲学書であると思う。2017/01/12
サトウ
3
否認、怒り、取引、抑鬱、受容の死の過程において、宗教や医師、または死に行く人など、さまざまな意見が描かれ、死を理解するというよりは、体感に近い感覚を覚える。しかし、この頭での理解(それが体感に近くあろうとも)は、死そのものを前にした時には粉々に砕け、なぜ今、この私が?ということは避けられないのだろう。どこかに書いてあったが、死は予想できない戦いなのだ。今持ってるものが価値をなくす恐ろしさ、そして二度と肉体としては生き返らないという不条理を前に、私はどうすればいいのか?どう生きるのか?常に問われている。2024/07/04
cocolate
3
著者の書いている部分と、他の人の論文がこんがらがってしまい、読むのに苦労してしまった。いつ死ぬのかは問題ではないということ。死も人生の一部であること。死にきること。2013/06/19